今、親の介護をしているあなた。
もしくは、そろそろ始まるかもしれない…と
心のどこかで感じているあなたへ。
「逃げたい」って思ったこと、ありませんか?
その気持ち、実はとっても大事なんです。
今日は、介護者にこそ必要な
“逃げる力”について、やさしくお話しします。
リアルな苦しみと現実

介護が始まると、日々の暮らしが一変します。
時間も、体力も、心も
少しずつ、少しずつ、削られていく。
そんな感覚を、抱えていませんか?
でも──
多くの人が言います。
「家族なんだから、がんばらなきゃ」
「私しかいないから」
「逃げちゃいけない」って。
その想いが、あなたを支えている一方で、
じわじわと、あなたを追いつめているかもしれません。
しなやかに生きる力
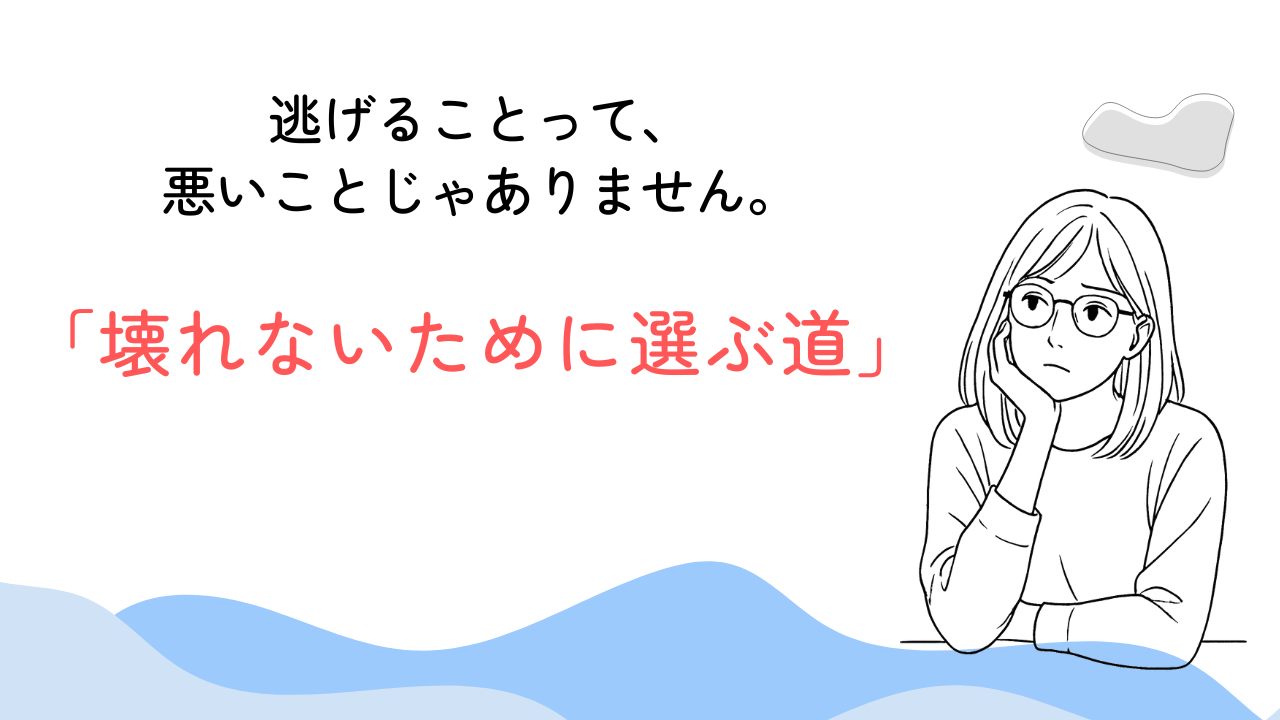
古いことわざに、こんな言葉があります。
「川に逆らって泳ぐより、流れに身を任せよ」
頑張り続けることは、美徳のように思われがち。
でも実は、流れに逆らい続けると、
心が壊れてしまうことがあるんです。
逃げることって、悪いことじゃありません。
それは「壊れないために選ぶ道」。
「しなやかに生きる力」なんです。
なぜ、逃げることが難しいのか?

まず、介護の現場では
「逃げたい」と感じることに
罪悪感を覚える人がとても多いんです。
「親が困ってるのに、自分だけ楽になっていいの?」
「申し訳ない、無責任に感じる…」
そんな声をたくさん聞きます。
でもね、忘れないでほしいことがあります。
あなたが壊れてしまったら、
親も、あなた自身も、もっと大変になるんです。
だからまずは、逃げることを「悪いこと」と思わないで。
それは、自分と大切な人を守る「勇気」なんです。
逃げる力って、どう身につけるの?
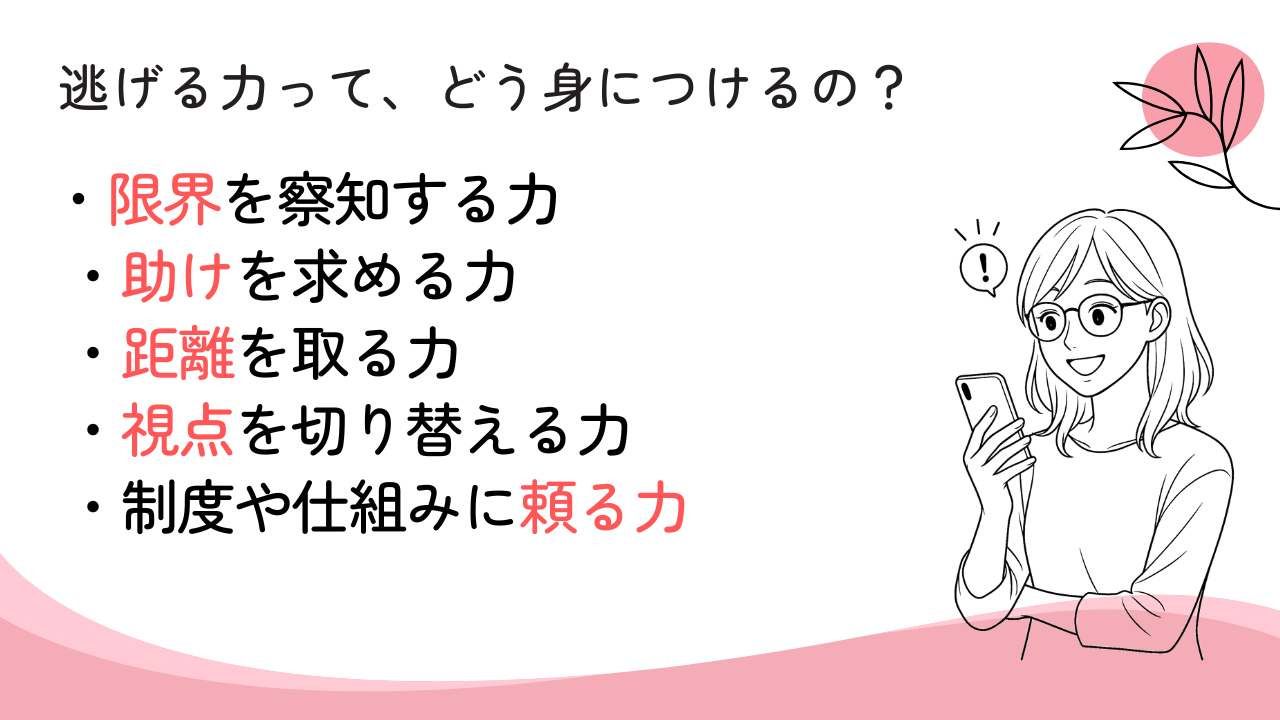
逃げる力とは、「放棄」や「投げ出し」ではありません。
それは──
・限界を察知する力
・助けを求める力
・距離を取る力
・視点を切り替える力
・制度や仕組みに頼る力
この5つの力のこと。
順番に見ていきましょう。
限界を察知する力
まず、自分の「限界」に気づくこと。
我慢強い人ほど、無意識に越えてしまいがちです。
毎日イライラする、眠れない、食欲がない、
言葉が荒くなる──
それは、心と身体からのSOSです。
「まだ頑張れる」は、「もう限界」に近づいてる証拠かもしれません。
助けを求める力
「助けて」が言える人は、弱い人じゃない。
むしろ、信頼できる強さを持った人です。
地域包括支援センター、ケアマネジャー、
介護者カフェ、訪問看護、ショートステイ…
手を伸ばせば、つかめる支援はたくさんあります。
制度の扉は、叩いた人にだけ開かれる。
一人で抱え込まず、まずは話すことから始めてみませんか。
距離を取る力
物理的にも、精神的にも、距離はとても大切です。
たとえば「週1回は家を出る」「1日だけショートステイを使う」
それだけでも、心のバランスが大きく変わります。
介護から“完全に離れる時間”は、
リセットボタンのようなもの。
一度離れることで、またやさしくなれる自分に戻れます。
視点を切り替える力
「なんでこんなに大変なのに…」と思う日もあります。
でも視点を変えると、
「今日も無事に終わった」
「ごはん、ちゃんと食べてくれた」
そんな小さな光にも気づけるようになります。
大きな希望じゃなくていい。
小さな嬉しさを拾える力を、大切にしてください。
頼る力(制度に乗る勇気)
厚生労働省や各自治体が提供している
介護支援制度を知ることは、逃げ道をつくる第一歩です。
・介護保険サービス(訪問介護、通所介護など)
・家族介護者支援(リフレッシュ事業や相談窓口)
・成年後見制度(判断力が低下した親の金銭管理)
制度は“逃げるための道具”ではなく
“あなたを支えるための装備”です。
まとめ
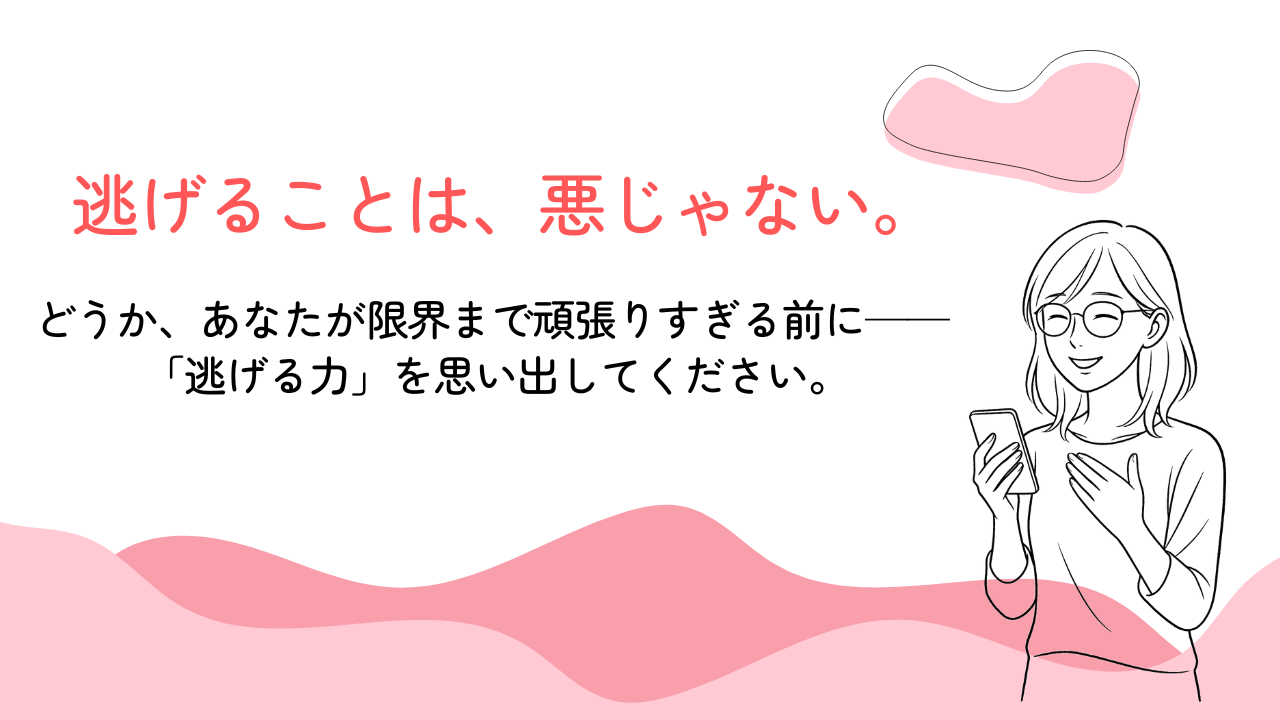
今日のお話、いかがでしたか?
介護の現場は、日常と表裏一体のもの。
でも、誰かのケアを続けるには、
まず自分の心と身体を守ることが最優先です。
逃げることは、悪じゃない。
それは、あなた自身と大切な人を
守るための“選択肢”なんです。
どうか、あなたが限界まで頑張りすぎる前に──
「逃げる力」を思い出してください。
もし、今少しでも「疲れたな」と感じたら
まずは、お近くの地域包括支援センターに
電話してみてください。
「相談したいだけ」でも、十分です。
話すこと。
手放すこと。
頼ること。
それは、あなたの優しさを長く保つための、大切な“準備”なんです。

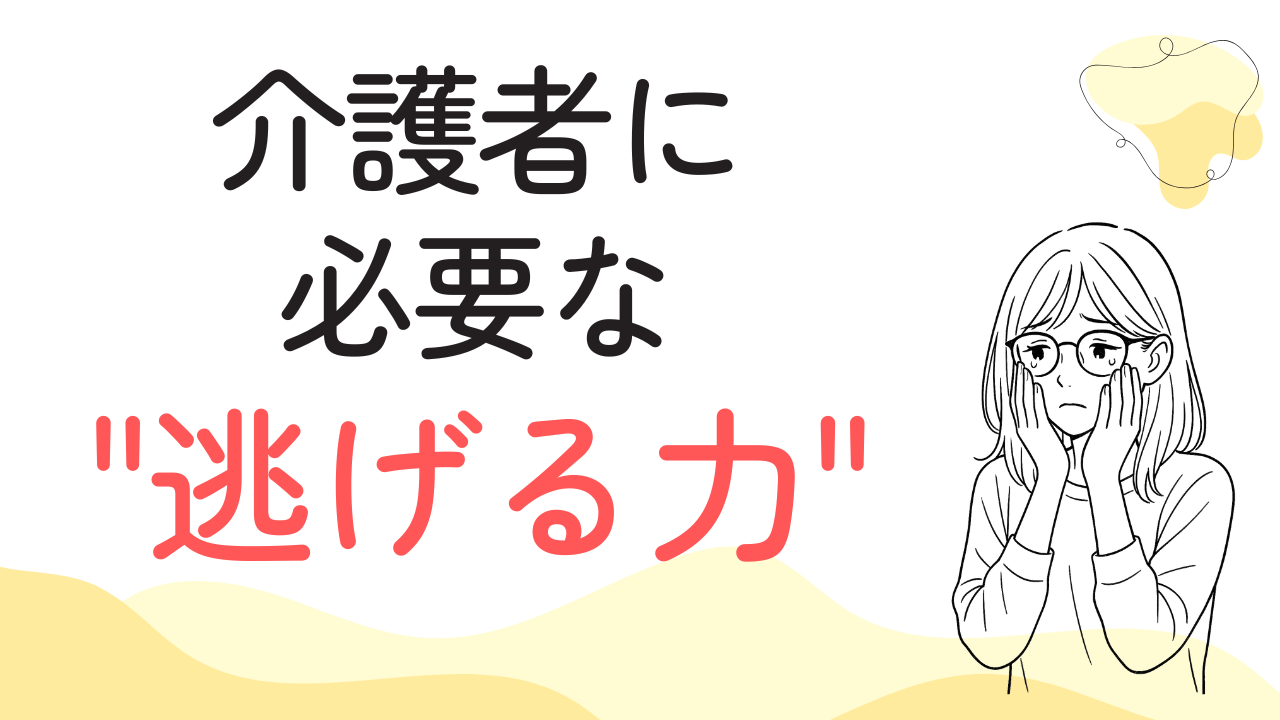
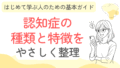
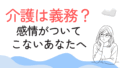
コメント