「うちの親、もしかして認知症かも…?」
そんな不安を抱えたとき、多くの人がまず戸惑うのが、
「認知症って何?どうやって進むの?種類ってあるの?」という基本的なこと。
認知症は“ひとつの病気”ではなく、いくつかのタイプ(原因)に分かれていることをご存じですか?
この記事では、認知症の主な種類とその特徴を、やさしい言葉で整理してお伝えします。
「初めて知る方」にこそ読んでいただきたい内容です。
動画解説
■ 認知症は「症状」ではなく「状態の総称」
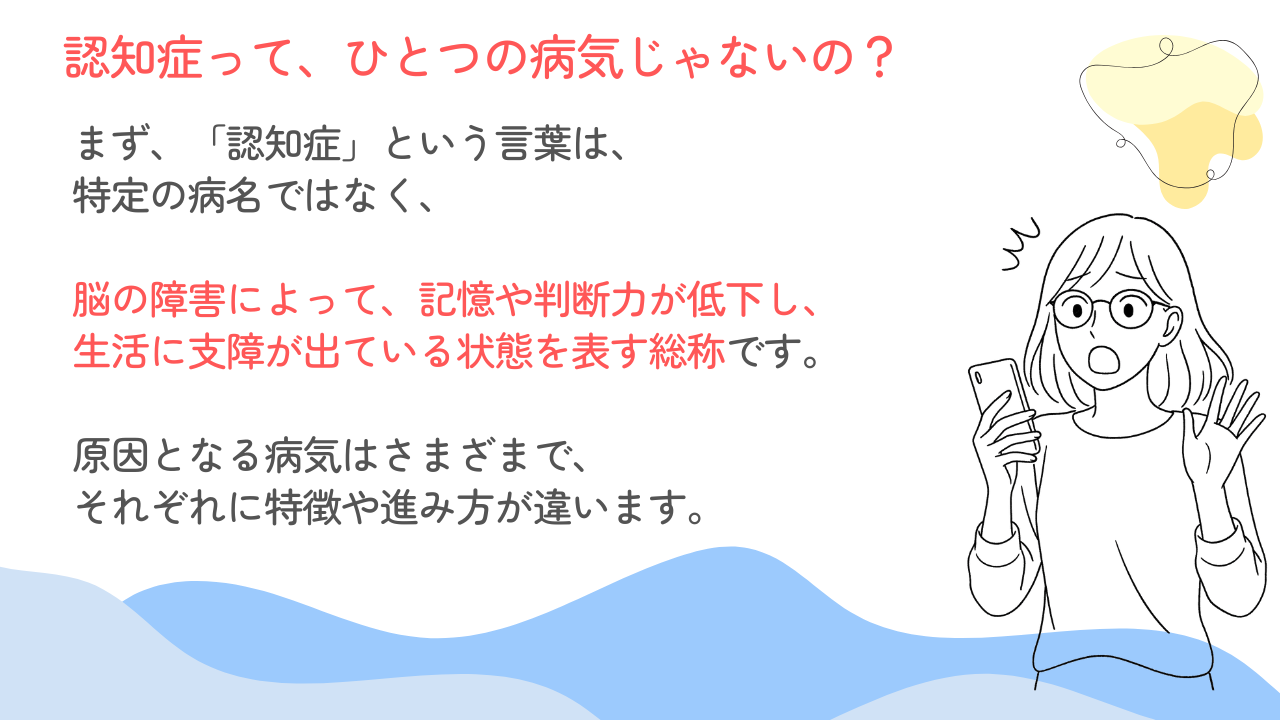
まず、誤解されがちですが──
「認知症」は、ひとつの病気の名前ではありません。
正式には、「病気や障害によって脳の働きが低下し、生活に支障が出る状態」を広く指す言葉です。
その原因となる病気には、いくつかの種類があり、
症状の出方や進み方も、それぞれ異なります。
■ 認知症の主な4つの種類
① アルツハイマー型認知症(全体の約6割)
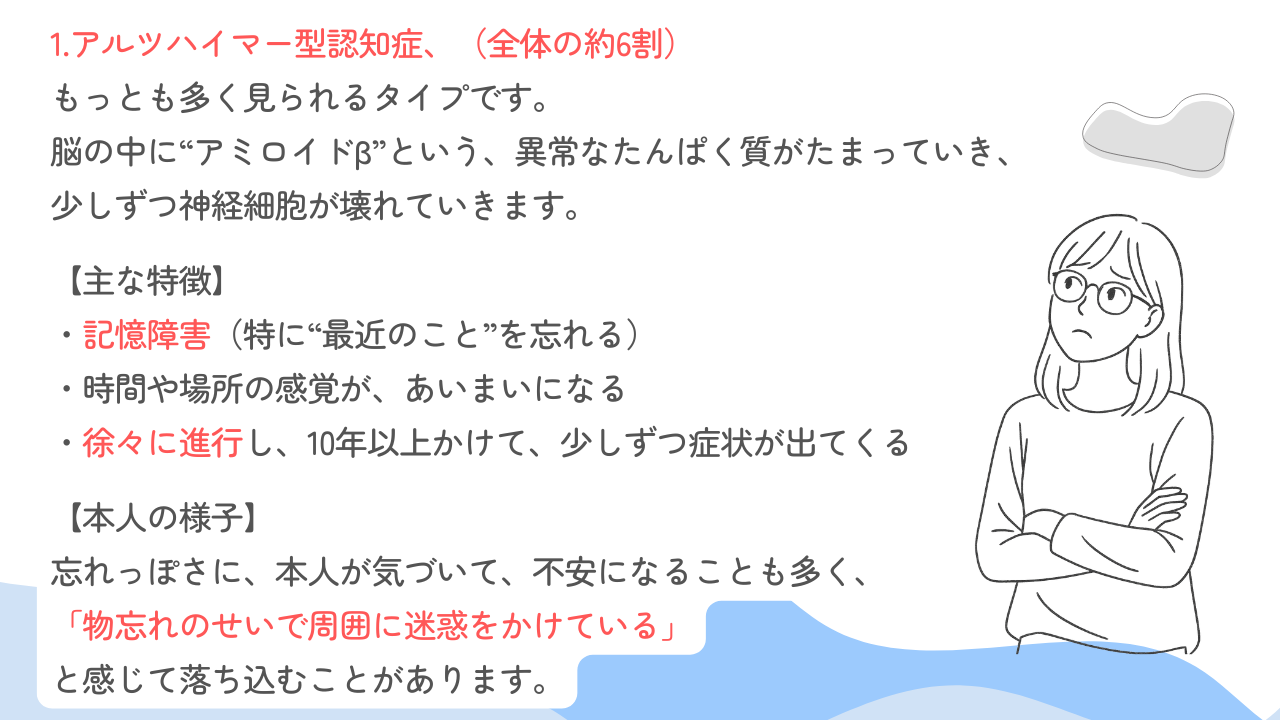
もっとも多く見られるタイプです。
脳の中に“アミロイドβ”という異常なたんぱく質がたまっていき、
少しずつ神経細胞が壊れていきます。
【主な特徴】
-
記憶障害(特に“最近のこと”を忘れる)
-
時間や場所の感覚があいまいになる
-
徐々に進行し、10年以上かけて少しずつ症状が出てくる
【本人の様子】
忘れっぽさに本人が気づいて不安になることも多く、
「物忘れのせいで周囲に迷惑をかけている」と感じて落ち込むことがあります。
② 脳血管性認知症(全体の約2割)
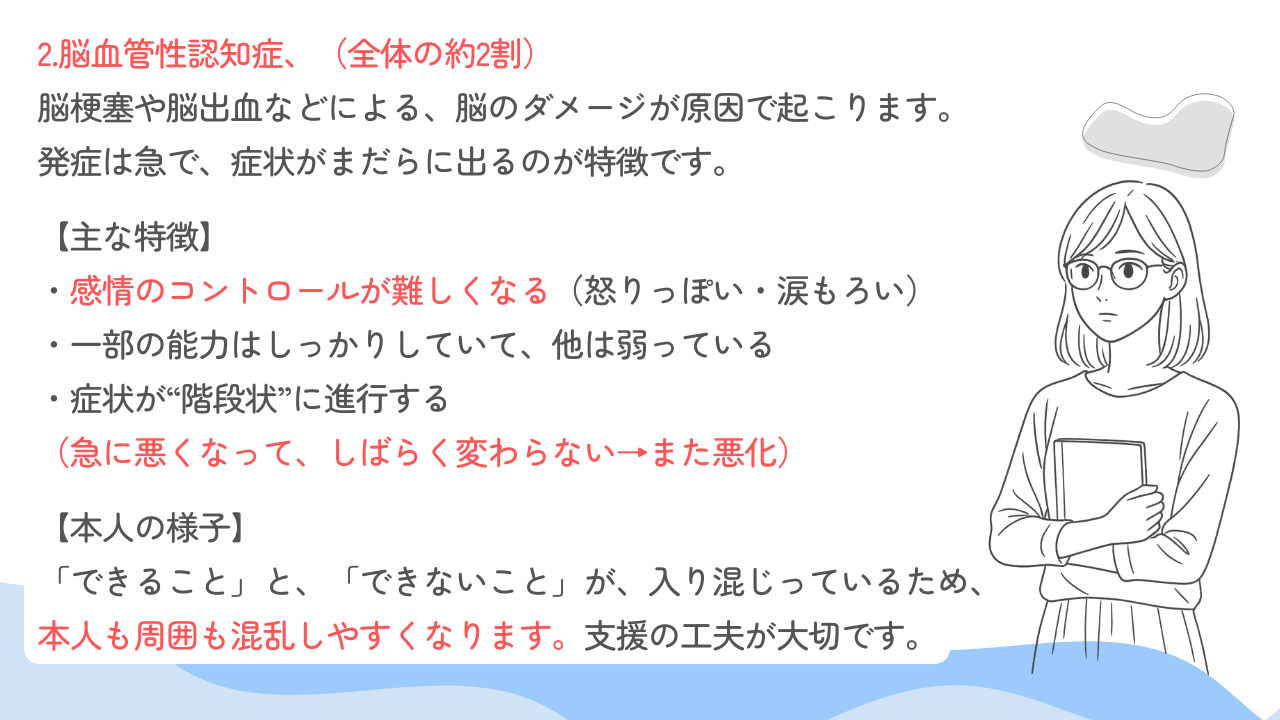
脳梗塞や脳出血などによる脳のダメージが原因で起こります。
発症は急で、症状がまだらに出るのが特徴です。
【主な特徴】
-
感情のコントロールが難しくなる(怒りっぽい・涙もろい)
-
一部の能力はしっかりしていて、他は弱っている
-
症状が“階段状”に進行する(急に悪くなって、しばらく変わらない→また悪化)
【本人の様子】
「できること」と「できないこと」が入り混じっているため、
本人も周囲も混乱しやすくなります。支援の工夫が大切です。
③ レビー小体型認知症(全体の1〜2割)
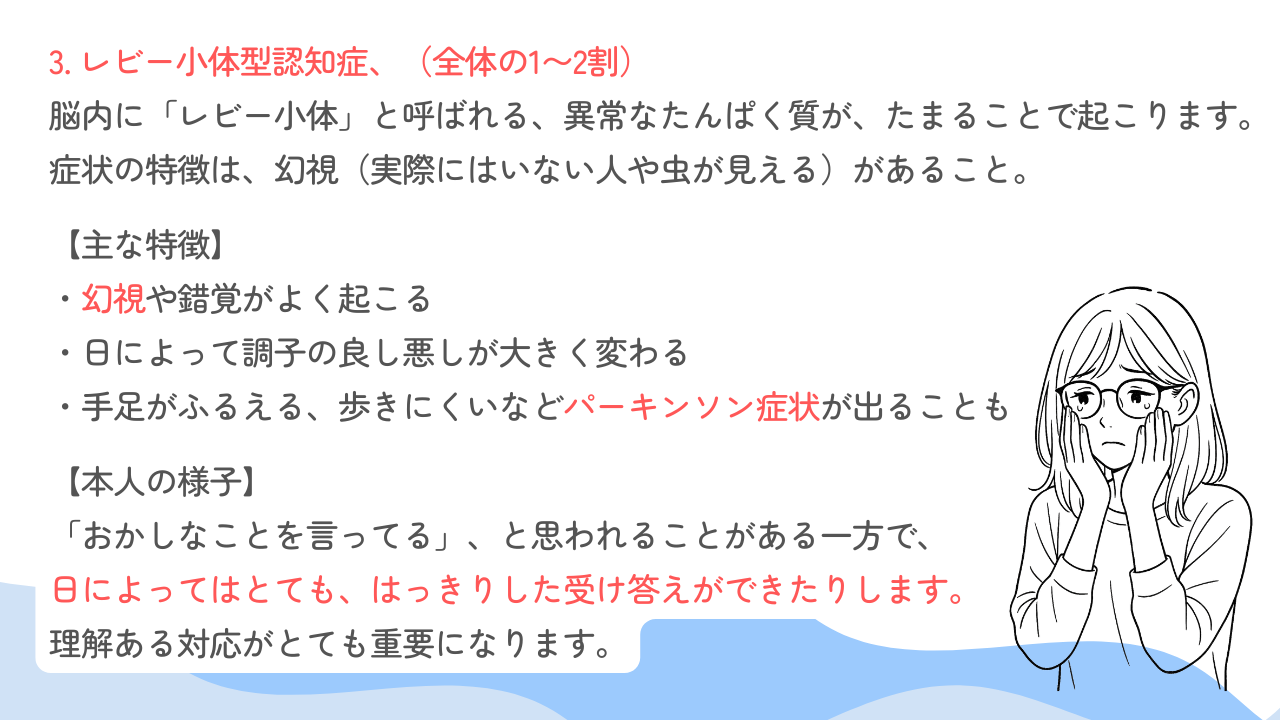
脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質がたまることで起こります。
症状の特徴は、**幻視(実際にはいない人や虫が見える)**があること。
【主な特徴】
-
幻視や錯覚がよく起こる
-
日によって調子の良し悪しが大きく変わる
-
手足がふるえる、歩きにくいなどパーキンソン症状が出ることも
【本人の様子】
「おかしなことを言ってる」と思われることがある一方で、
日によってはとてもはっきりした受け答えができたりします。
理解ある対応がとても重要になります。
④ 前頭側頭型認知症(ピック病など)
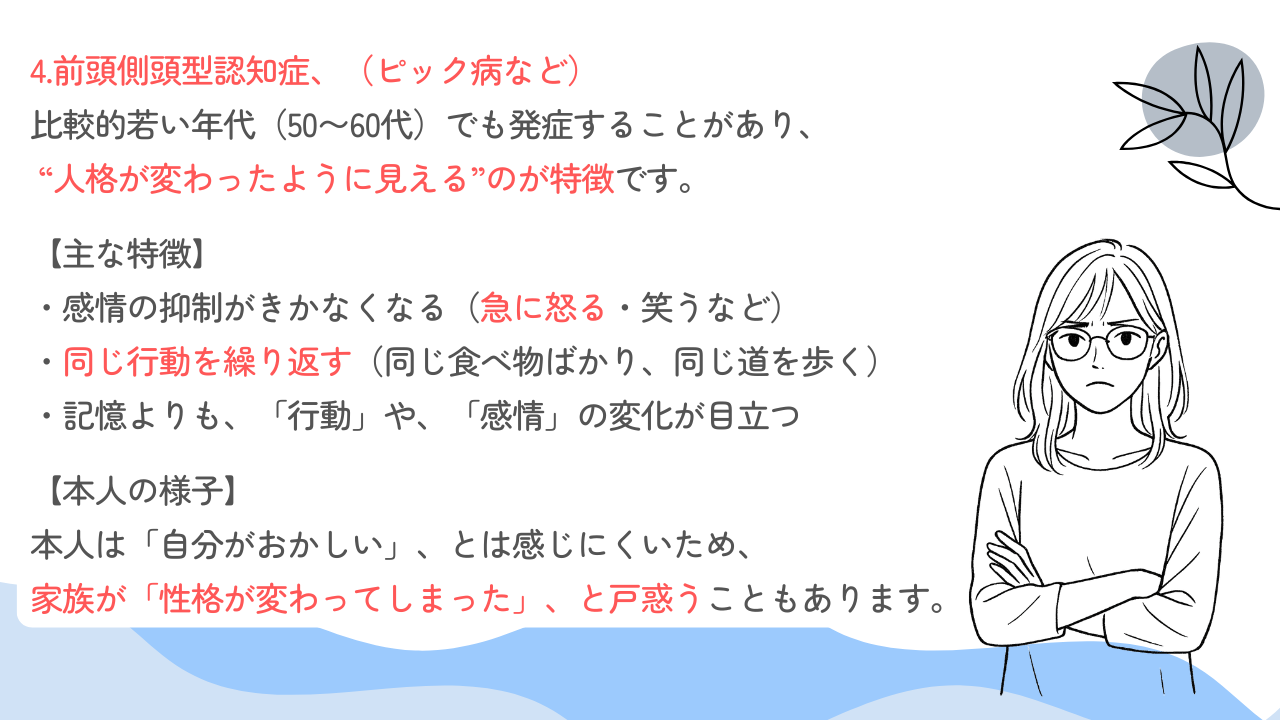
比較的若い年代(50〜60代)でも発症することがあり、
“人格が変わったように見える”のが特徴です。
【主な特徴】
-
感情の抑制がきかなくなる(急に怒る・笑うなど)
-
同じ行動を繰り返す(同じ食べ物ばかり、同じ道を歩く)
-
記憶よりも「行動」や「感情」の変化が目立つ
【本人の様子】
本人は「自分がおかしい」とは感じにくいため、
家族が「性格が変わってしまった」と戸惑うこともあります。
■ 間違えやすい「加齢による物忘れ」との違い
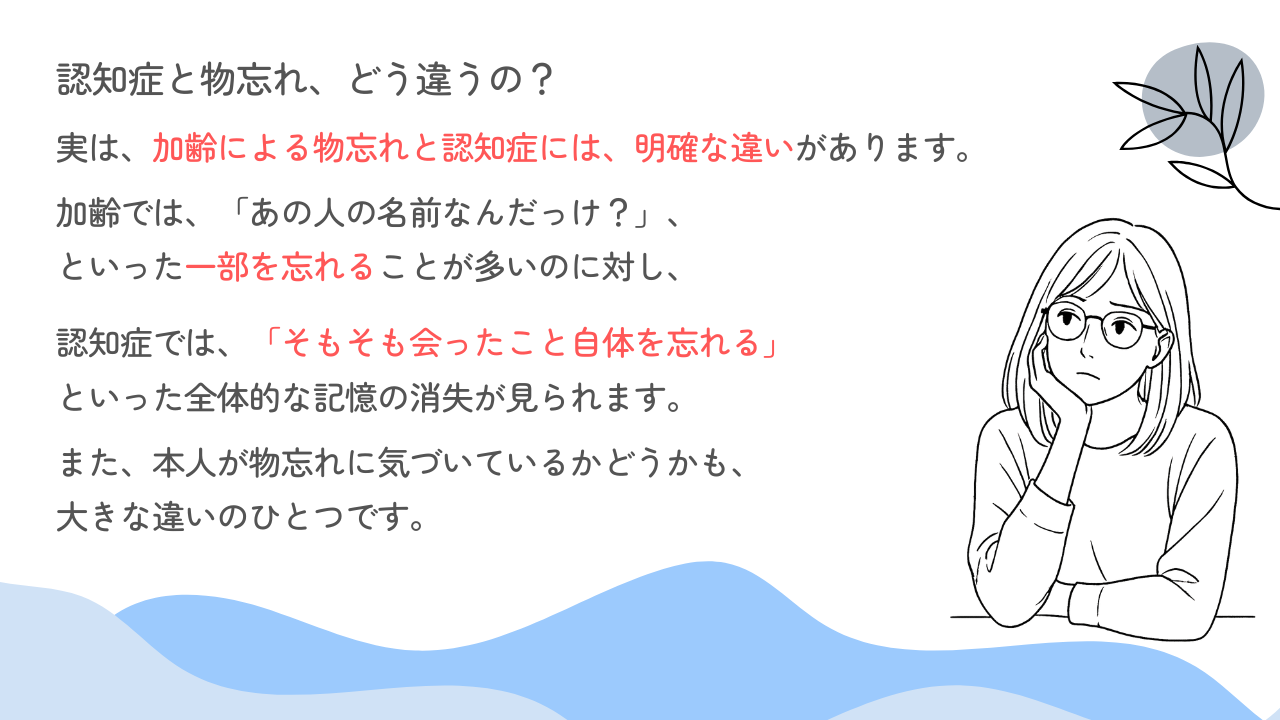
「認知症かな?それとも年齢のせい?」と感じる場面も多いかもしれません。
以下のような違いがあります:
| 項目 | 加齢による物忘れ | 認知症の物忘れ |
|---|---|---|
| 忘れ方 | 一部を忘れる(例:名前が出てこない) | 体験そのものを忘れる(例:会ったこと自体を忘れる) |
| 気づき | 本人が自覚していることが多い | 本人が気づかないことが多い |
| 生活への影響 | 日常生活に支障は少ない | 支障が出てくる(たとえば買い物や料理ができないなど) |
■ まとめ:種類を知ることは、「寄り添い方」を学ぶこと
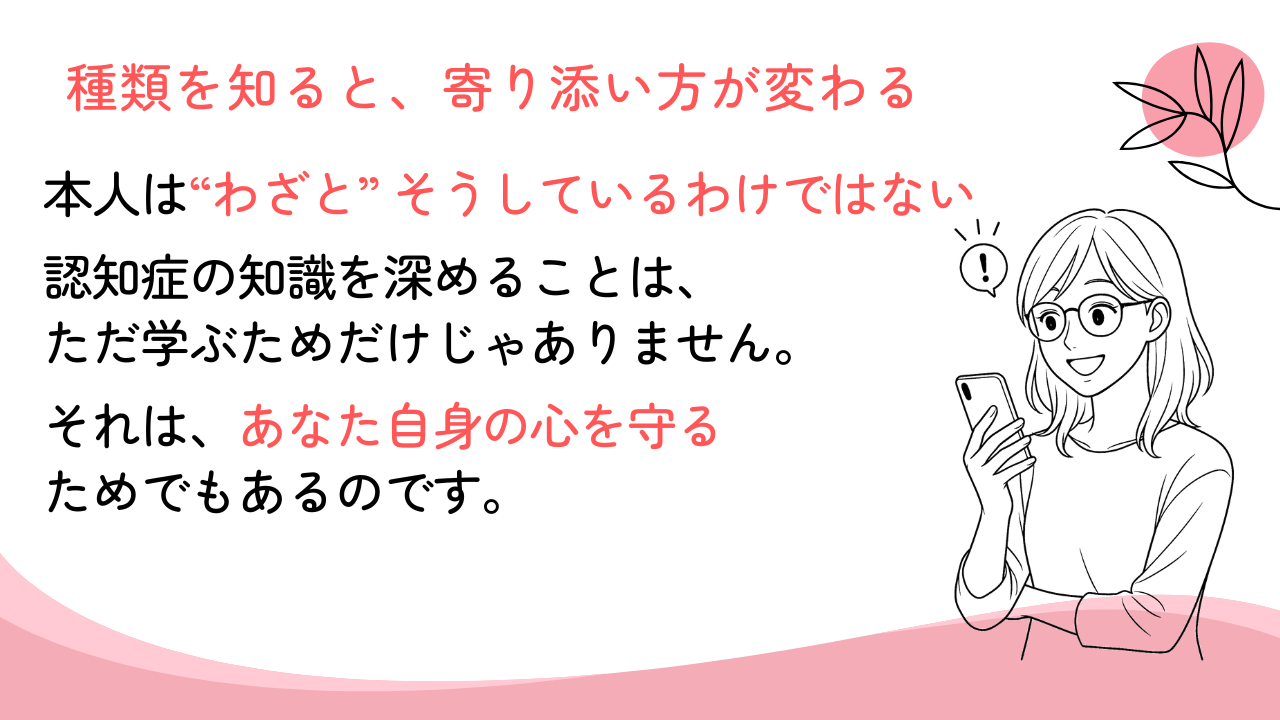
認知症とひとことで言っても、そのタイプによって現れ方はさまざま。
でも共通して言えるのは──
本人は決して“わざと”そうしているわけではないということ。
大切なのは、「その人の変化」にただ驚いたり責めたりするのではなく、
“なぜ、そうなるのか”という背景を知ることです。
そうすれば、対応のヒントも見えてきますし、
なにより、本人との信頼関係も育っていきます。
こんにちは、ナビゲーターのアイです。
認知症にはいろんな形があります。
そしてそのすべてに、“その人らしさ”が残っています。知ることで、怖さが減っていく。
あなたが少しずつ学んでいけるように、
アイはこれからも、そっと寄り添っていきます。

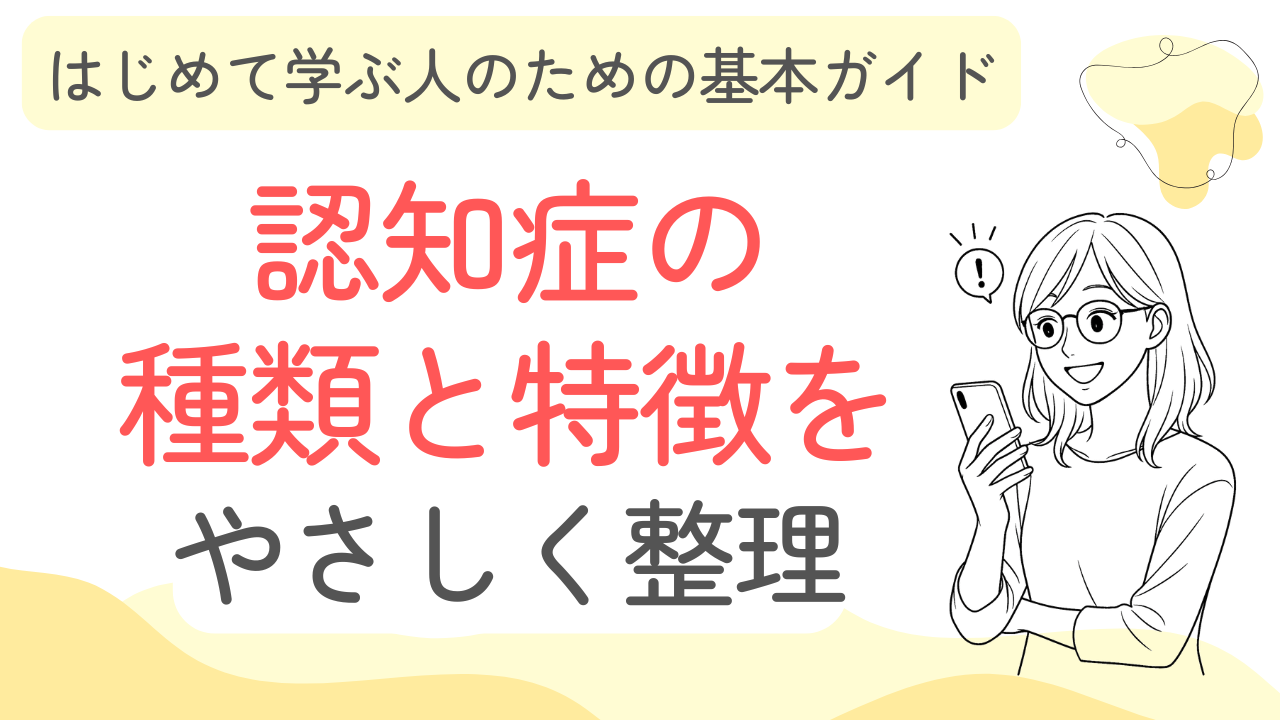
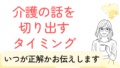
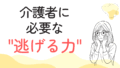
コメント