今日は、とても大切なお話をします。
もし、親の命に関わる決断を突然、あなたがしなければならなくなったら……。
延命治療をするのか。 それとも、自然な最期を見守るのか。
これは、正解のない問いです。 でも、多くの人が、“本人の意思がわからないまま”選ばされてしまう現実があります。
今日は、そんな“選ばされる現場”で何が起きているのか、 そして、今できる小さな備えについて、一緒に考えていきませんか?
突然、延命治療の選択を迫られる日
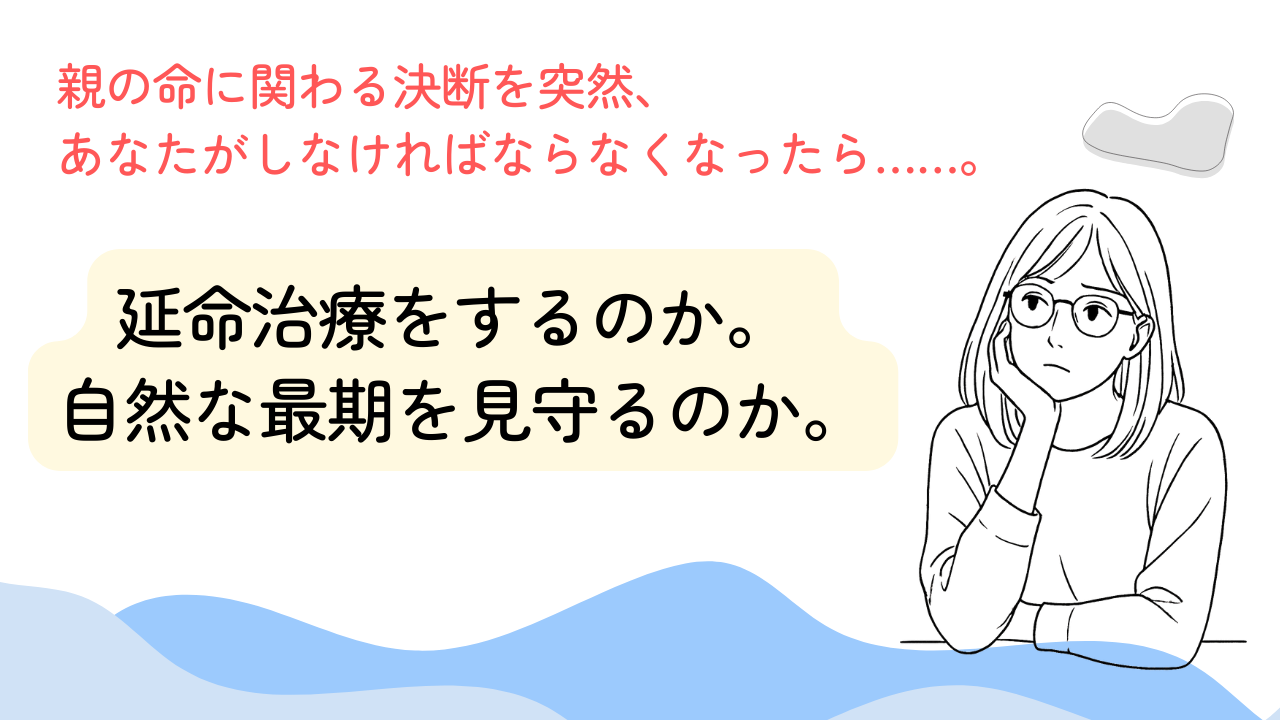
ある日のこと。
病院で、親の容体が急変。 医師から言われました。
「すぐにご家族の同意が必要です」
その言葉を聞いたとき、私は頭が真っ白になりました。
延命治療をするかどうか。
説明はありました。 でも、それは……“一方的な説明”でしかなかったのです。
私は頷くしかなくて。 気づいたら、延命前提で話が進んでいました。
形骸化された「インフォームドコンセント」
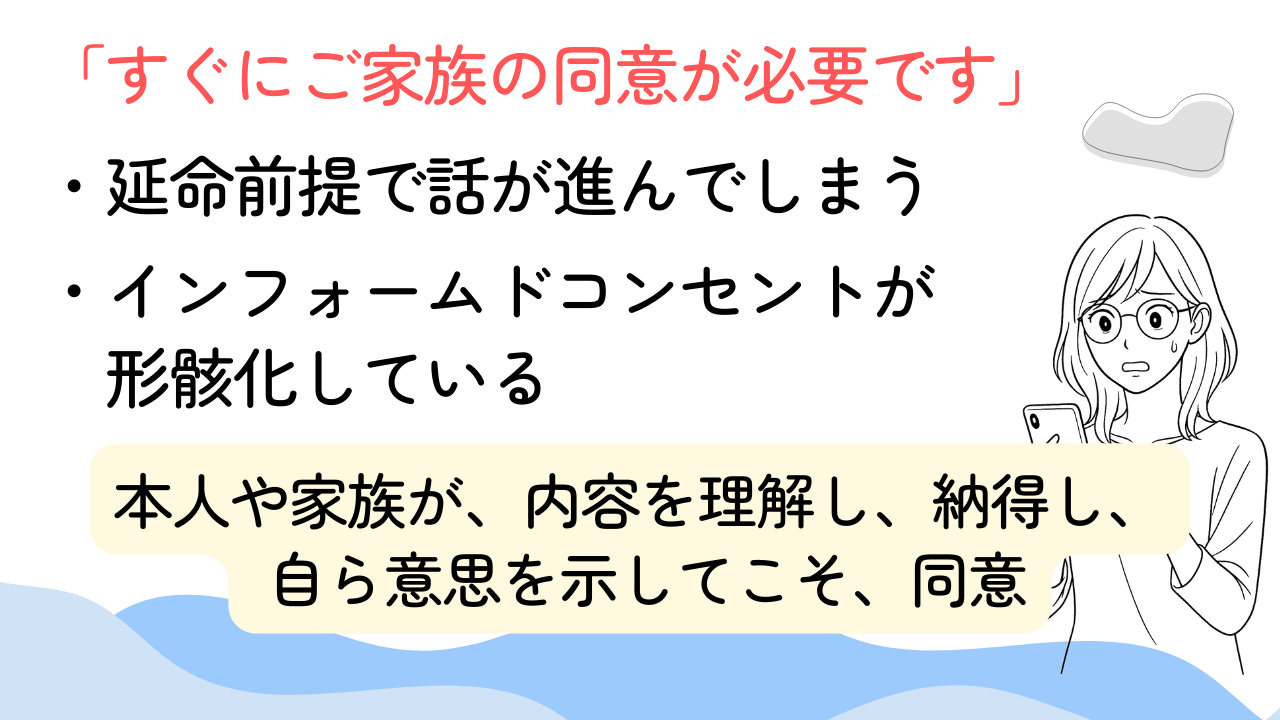
医師は、命を救うことを使命にしています。 だからこそ、延命は“当然の選択”とされがちです。
でも、私たち家族には、 「本人がどうしたいのか」 「本当にそれでいいのか」
……考える時間も、心の準備もありませんでした。
これが、“インフォームドコンセントが形骸化している”現場です。
本来、医療の同意は、説明を受けただけでは成立しません。
本人や家族が、内容を理解し、納得し、 自ら意思を示してこそ、同意なのです。
縁起でもないが、後の長い苦しみの始まり
でも、ほとんどの家庭では、 「親に延命したいかどうか、なんて聞けないよ…」 という空気があります。
わかります。 私もそうでした。
縁起でもないと思った。 元気なうちは、話す必要もないと思っていた。
でも、その“話さなかったこと”が、 あとで自分を、そして親を苦しめることになるなんて……。
誰も教えてくれなかった。
自分らしい最期はを守るのは家族
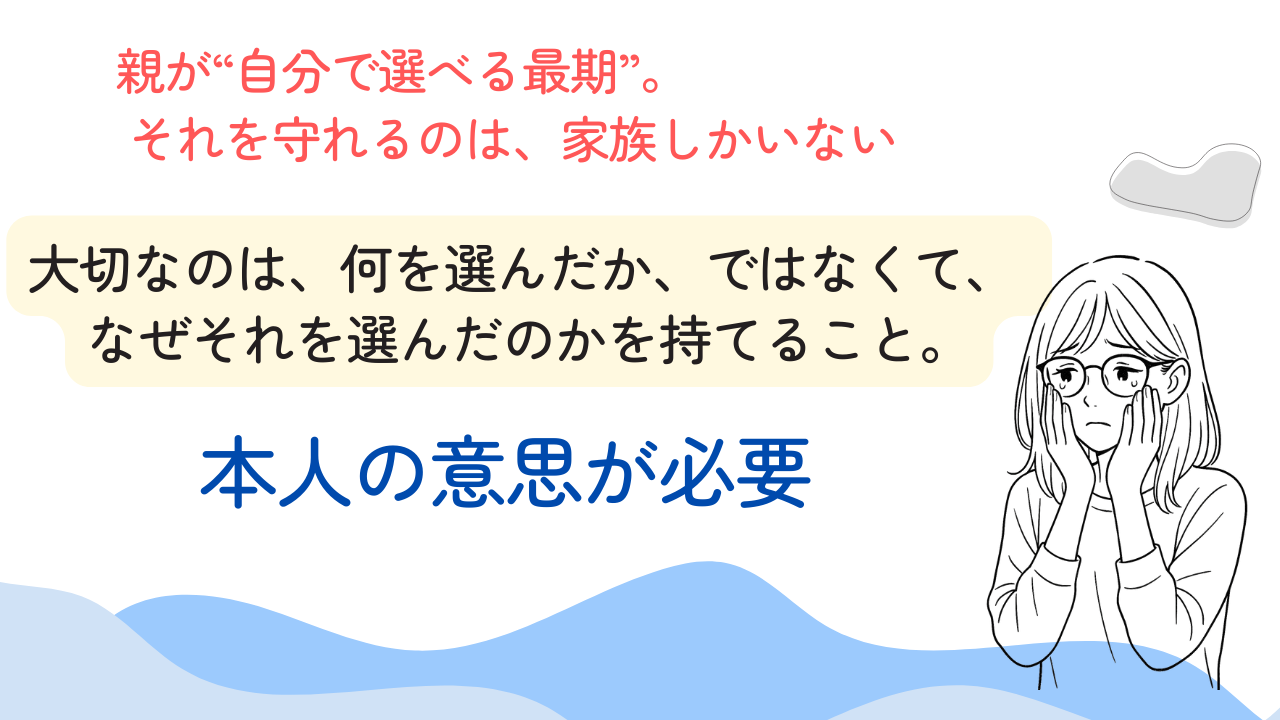
親が“自分で選べる最期”。 それを守れるのは、家族しかいません。
でも、本人が元気なうちにその機会をつくっておかないと、 家族が背負う責任は、とても重くなります。
延命治療をして、 「もっと自然に見送ってあげたかった」と悔やむ人もいます。
逆に、自然な最期を選んで、 「本当にこれでよかったのか」と苦しむ人もいます。
大切なのは、何を選んだか、ではなくて、 なぜそれを選んだのかを持てること。
そのためには、本人の意思が必要です。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)
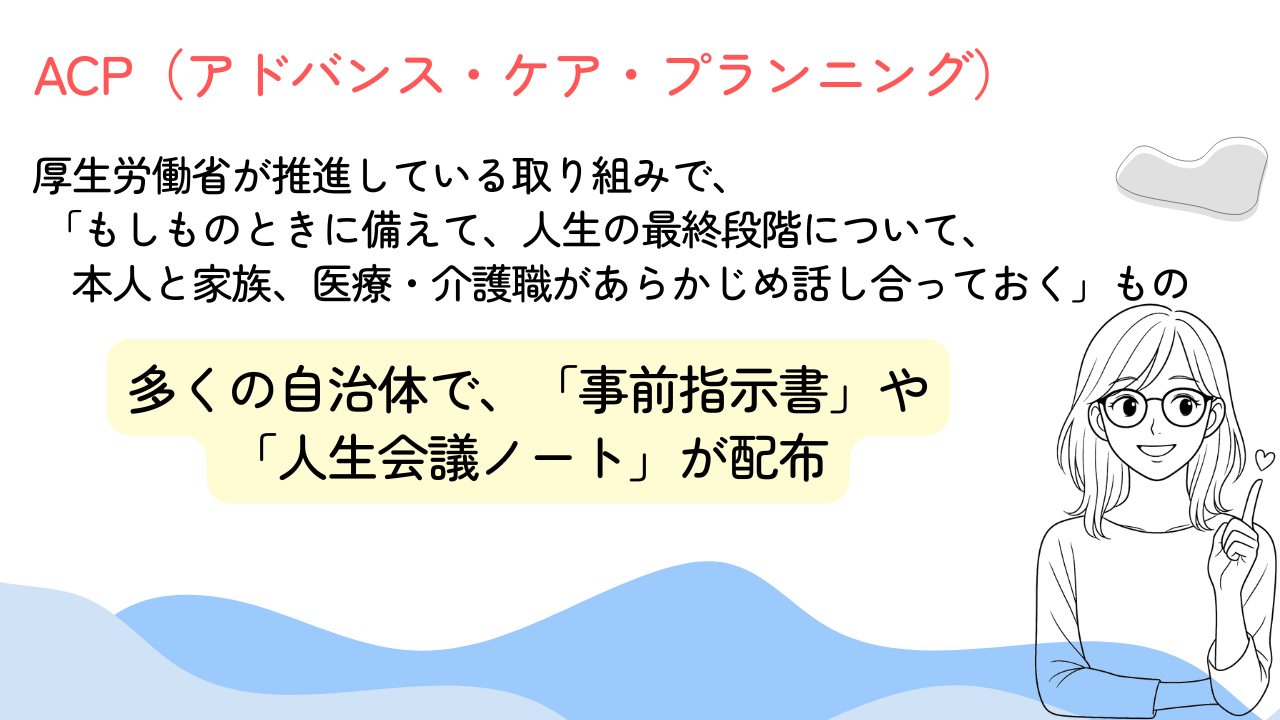
ここで知ってほしい制度があります。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)。
厚生労働省が推進している取り組みで、 「もしものときに備えて、人生の最終段階について、 本人と家族、医療・介護職があらかじめ話し合っておく」ものです。
いま多くの自治体で、「事前指示書」や「人生会議ノート」が配布されています。
・延命治療を希望するか ・人工呼吸器をつけてでも生きたいか ・最期はどこで迎えたいか
書いておくことで、いざというとき、家族の判断の負担が大きく軽減されます。
自然に自分らしく生きる
何よりも大切なのは、 「その人が、その人らしく、生ききる」こと。
老子が説くように、 自然に逆らわず、静かに受け入れる。
エピクロスが語るように、 恐れよりも、心の平穏を大切にする。
そんな視点で“最期”を考えたとき、 延命か自然死かは、手段のひとつでしかないのかもしれません。
今日から始められる3つの行動
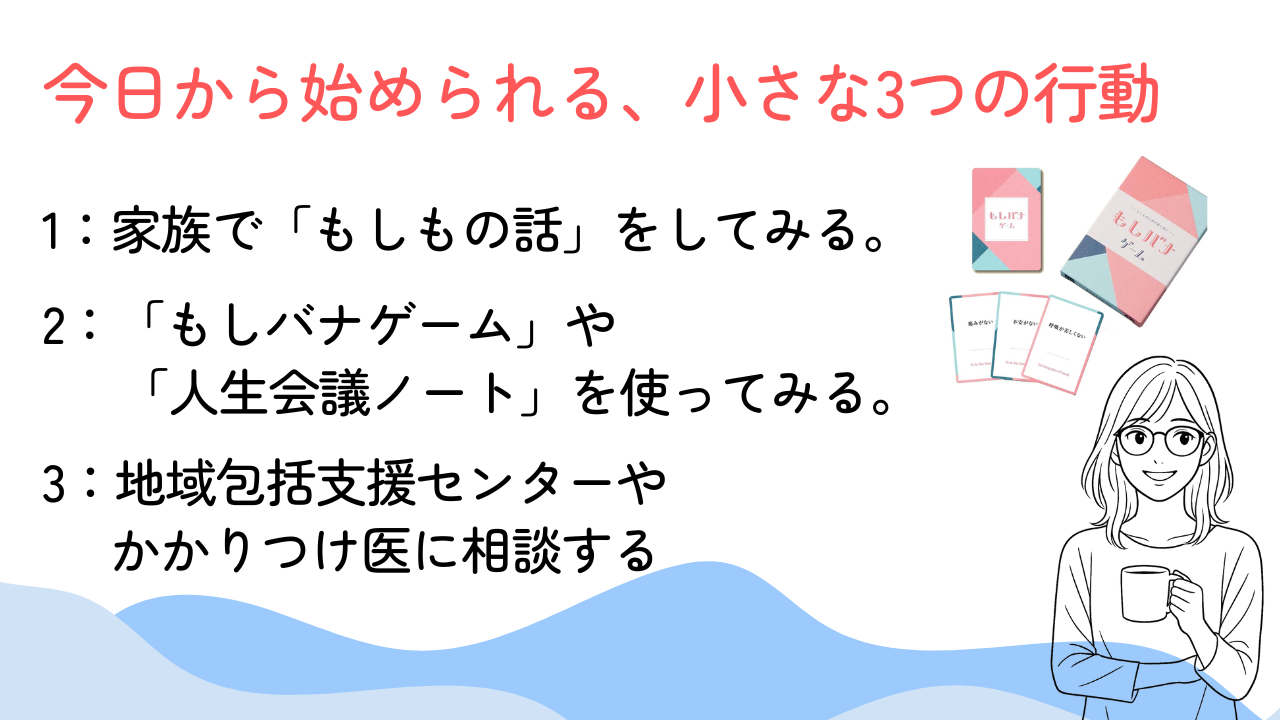
では、私たちは、どうすればいいのでしょうか。
今日から始められる、小さな3つの行動を提案します。
1つ目。家族で「もしもの話」をしてみる。 お正月や帰省時など、静かな時間に、そっと切り出してみる。
2つ目。「もしバナカード」や「人生会議ノート」を使ってみる。 質問形式で、気軽に意思を引き出せます。
3つ目。地域包括支援センターやかかりつけ医に相談する。 「どう話していいかわからない」と伝えるだけでも大丈夫。
延命治療に正解はないが、後悔しない根拠は作れる
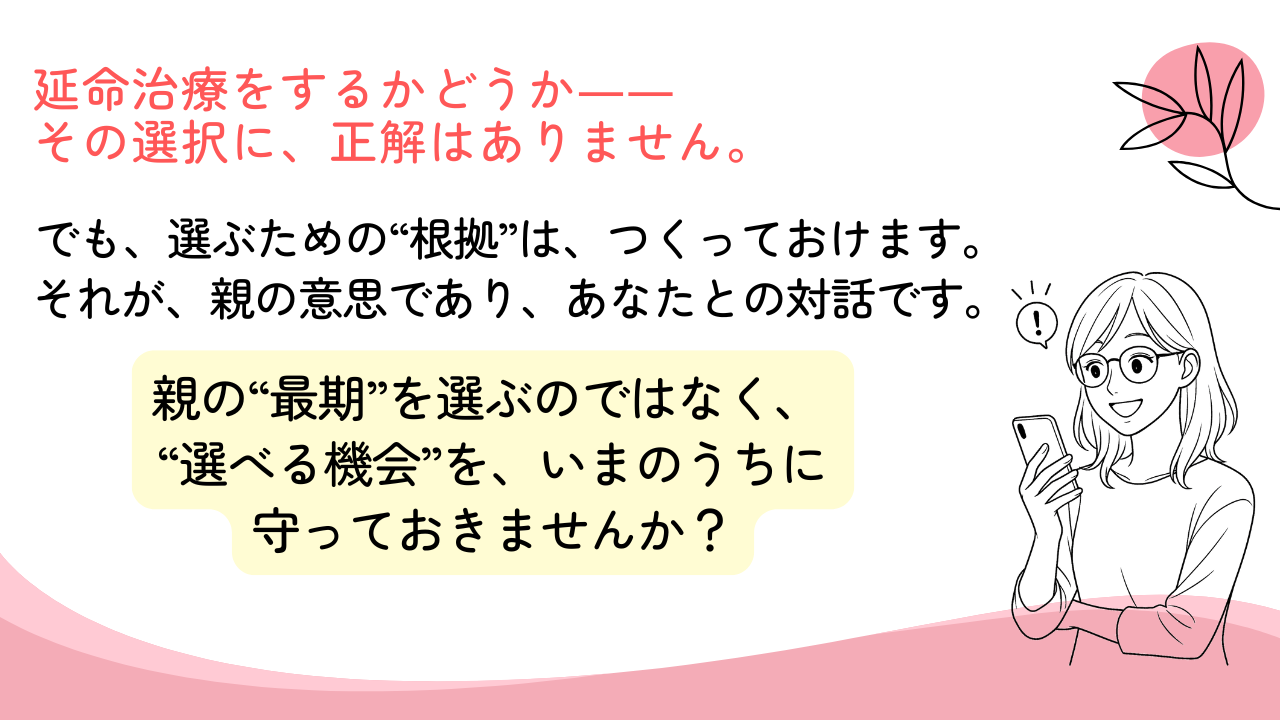
延命治療をするかどうか―― その選択に、正解はありません。
でも、選ぶための“根拠”は、つくっておけます。
それが、親の意思であり、あなたとの対話です。
親の“最期”を選ぶのではなく、 “選べる機会”を、いまのうちに守っておきませんか?
その小さな一歩が、 きっとあなた自身をも、救ってくれます。
あなたとご家族の心に、静かな安心が届きますように。

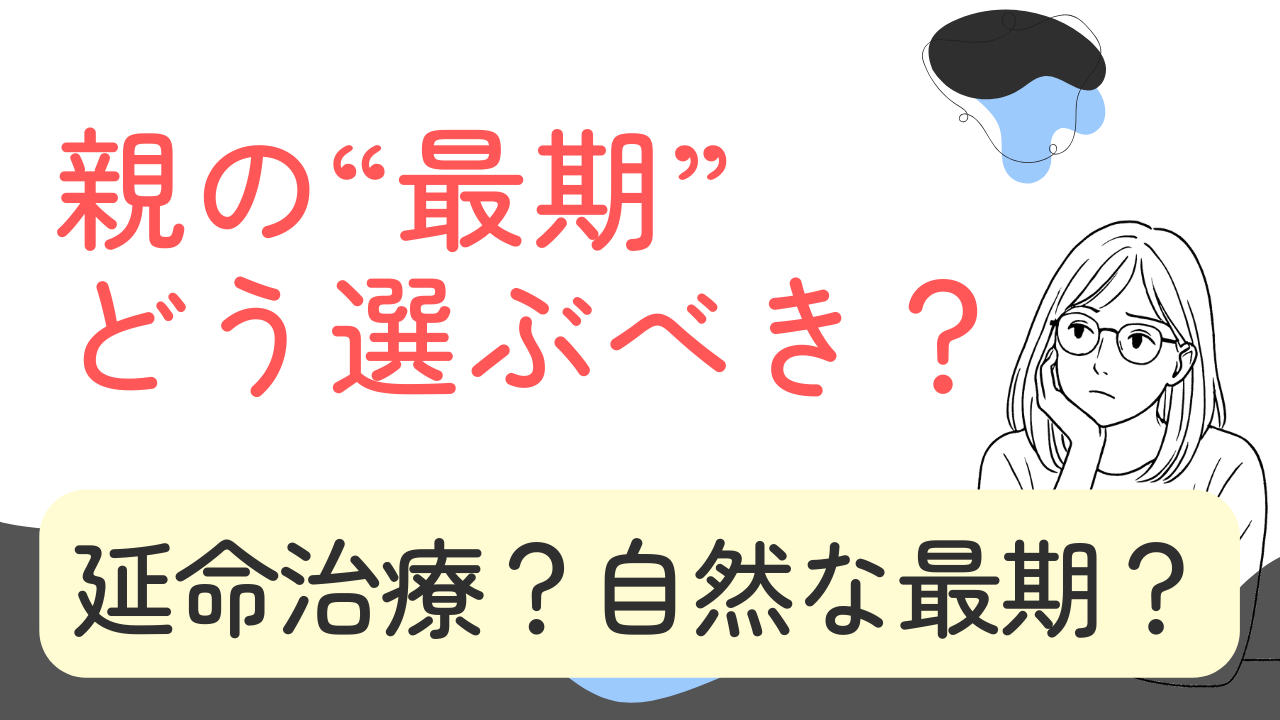

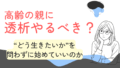
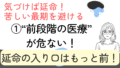
コメント