こんにちは、アイです。
もし、医師から「お父さま、透析が必要です」と言われたら──
あなたは、どうしますか?
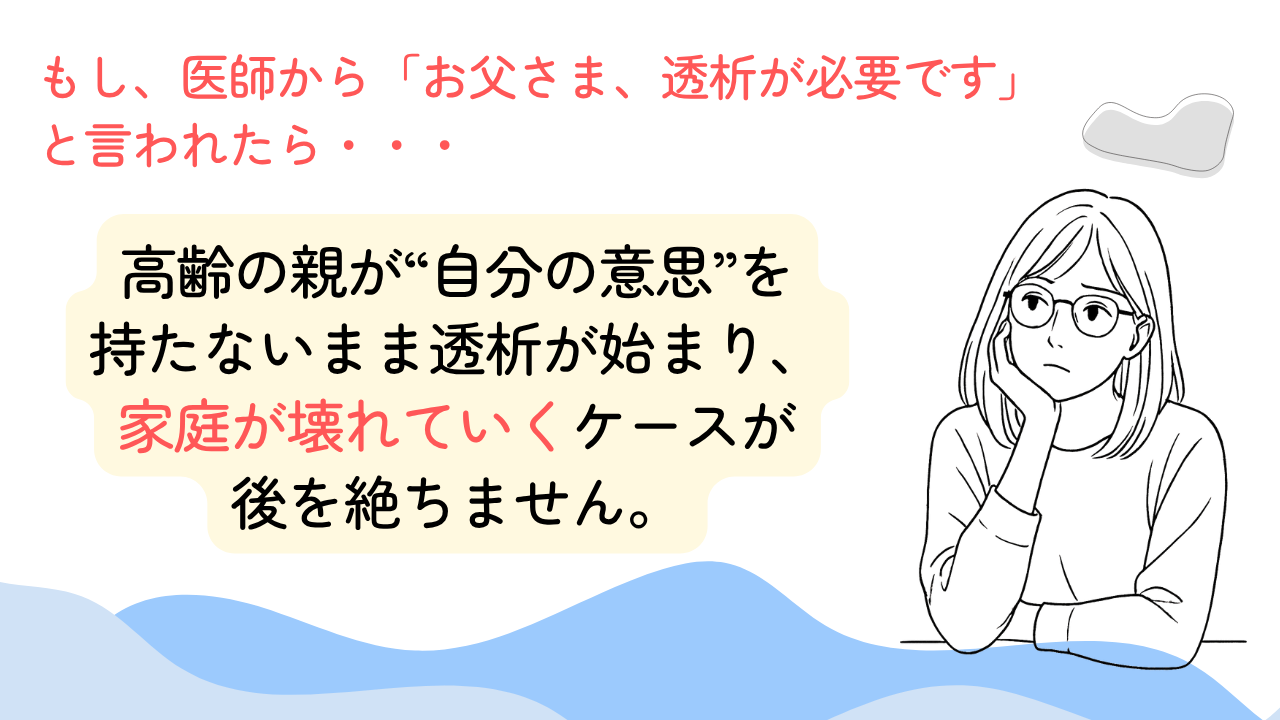
-
「やらないと死ぬんですか?」
-
「本人は、あまり自覚ないみたいで…」
-
「始めたほうがいいんですよね?」
その瞬間、答えられないのは当然です。
でも今、高齢の親が“自分の意思”を持たないまま透析が始まり、家庭が壊れていくケースが後を絶ちません。
今日は、「透析」という治療を通して、
“どう生きたいか”という根本の問いを一緒に考えてみたいと思います。
動画解説
本人不在の「透析導入」
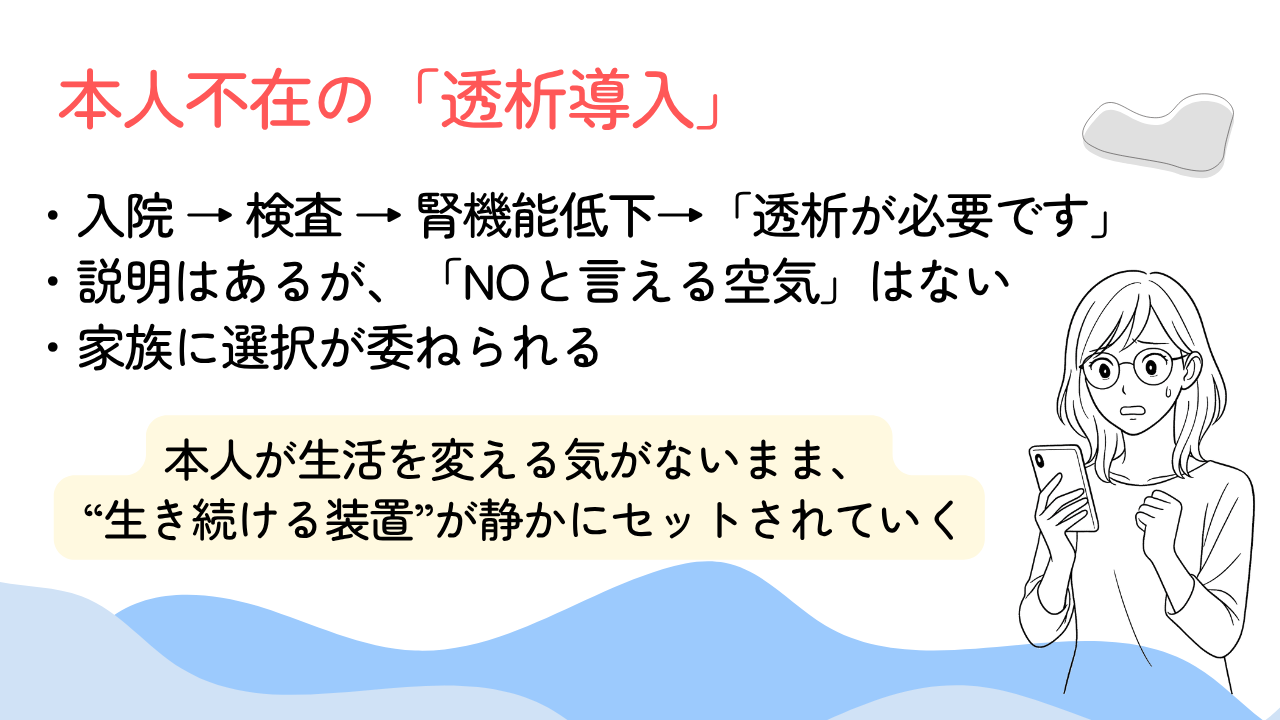
-
実際の流れ:入院 → 検査 → 腎機能低下 → 「透析が必要です」
-
説明はあるが、「NOと言える空気」はない
-
家族に選択が委ねられる:「やりますか?」「今日から準備しましょうか?」
多くの場合、本人はこう言います:
「先生が言うなら…」
「よくわからないから任せるよ」
「家で通えるなら、別にいいよ」
でも、本人が生活を変える気がないまま、
“生き続ける装置”が静かにセットされていく。
そして家族には、
「送迎」「病院付き添い」「栄養・水分管理」…
想像以上の現実が、押し寄せます。
「生活を変えたくない」親と、「背負わされる」家族
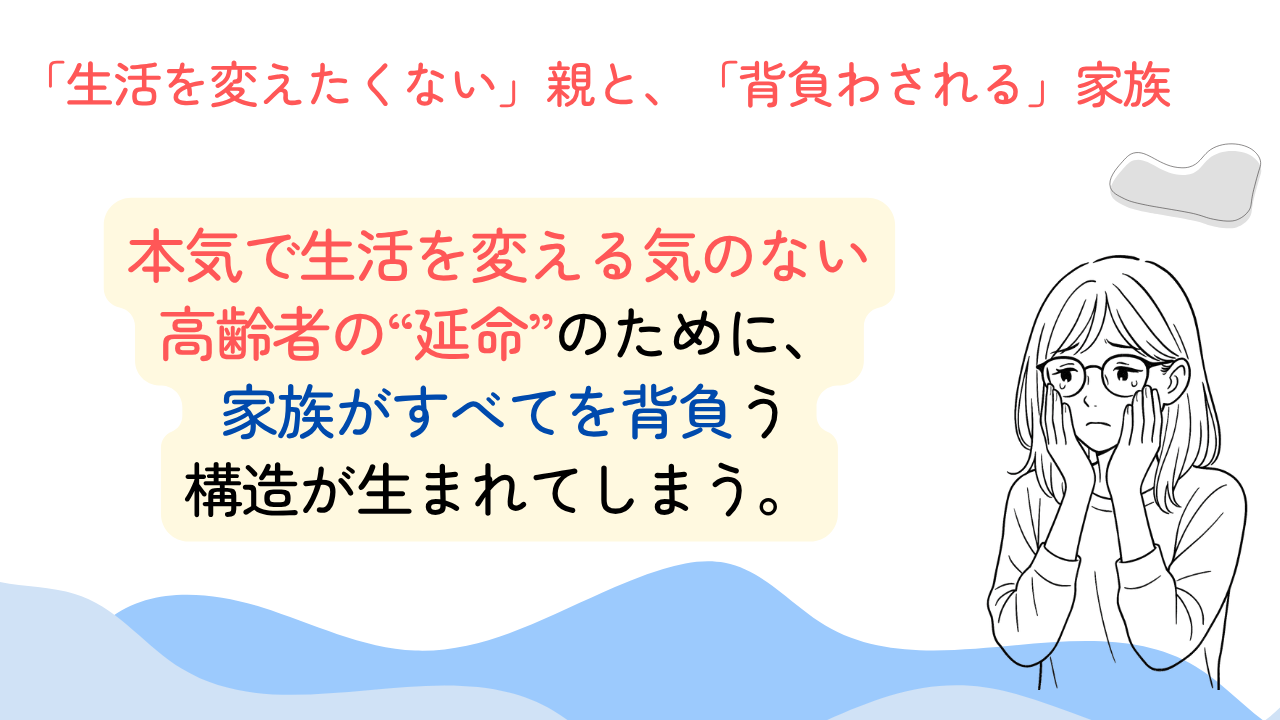
-
生活習慣病を放置してきた経緯
-
塩分・水分制限もせず、「病気は病院が治すもんだ」と他人事
-
透析は「本人の努力の結果」ではなく、「医療の責任」になっている
この結果、
本気で生活を変える気のない高齢者の“延命”のために、
家族がすべてを背負う構造が生まれてしまう。
あなたは今、こんなふうに感じていませんか?
-
「父のためと思って始めたけど、正直つらい」
-
「本人は通うだけで、何も変えようとしない」
-
「やめたいと思っても“命に関わる”と言われ、止められない」
腹膜透析・血液透析の現実と、制度の限界
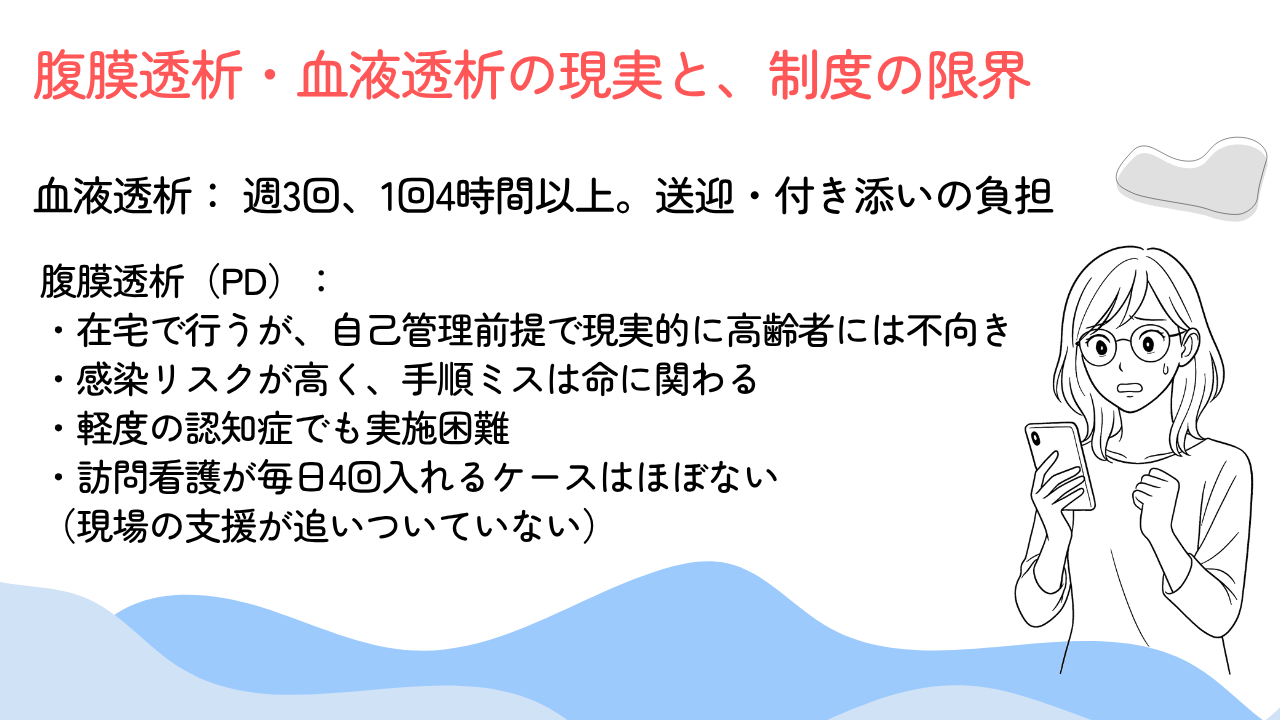
-
血液透析(HD): 週3回、1回4時間以上。送迎・付き添いの負担
-
腹膜透析(PD): 在宅で行うが、自己管理前提で現実的に高齢者には不向き
-
感染リスクが高く、手順ミスは命に関わる
-
軽度の認知症でも実施困難
-
訪問看護が毎日4回入れるケースはほぼない(現場の支援が追いついていない)
-
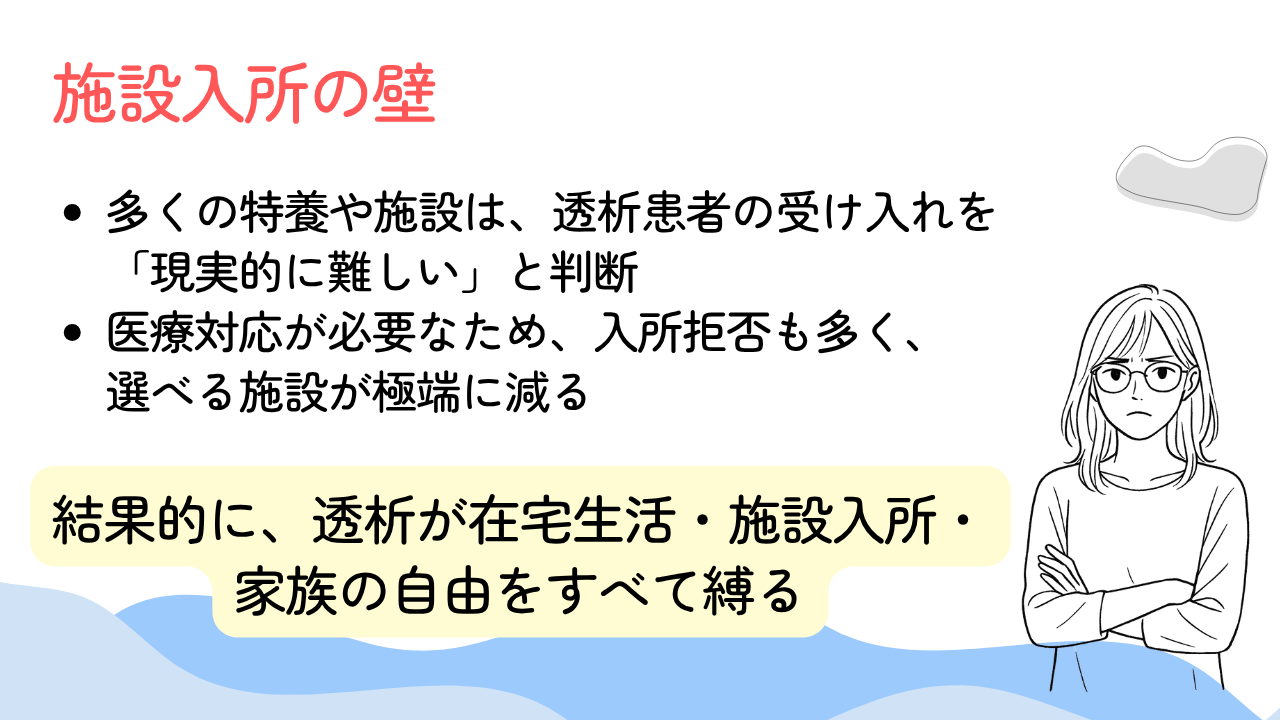
そしてもう一つの盲点が、施設入所の壁。
-
多くの特養や施設は、透析患者の受け入れを「現実的に難しい」と判断
-
医療対応が必要なため、入所拒否も多く、選べる施設が極端に減る
-
結果的に、透析が在宅生活・施設入所・家族の自由をすべて縛る
「治療するかどうか」ではなく、「どう生きたいか」を問う
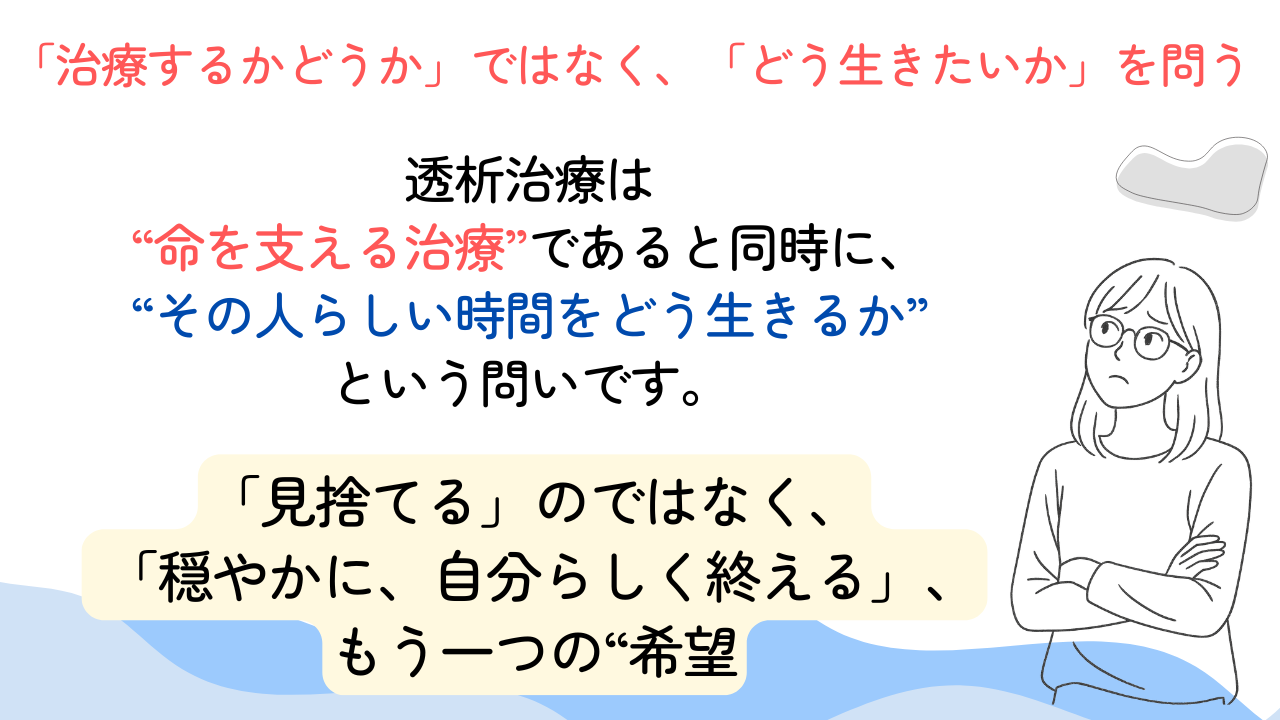
透析を始めるということは、
“命を支える治療”であると同時に、
“その人らしい時間をどう生きるか”という問いです。
高齢の親にとって、本当に幸せな選択とは──
-
長く生きることか
-
家族に迷惑をかけないことか
-
最後まで自分らしく生きることか
実は、「透析をしない」という選択肢もあります。
それは「見捨てる」のではなく、
「穏やかに、自分らしく終える」という、もう一つの“希望”です。
今、透析という選択を前にして悩んでいる方へ。
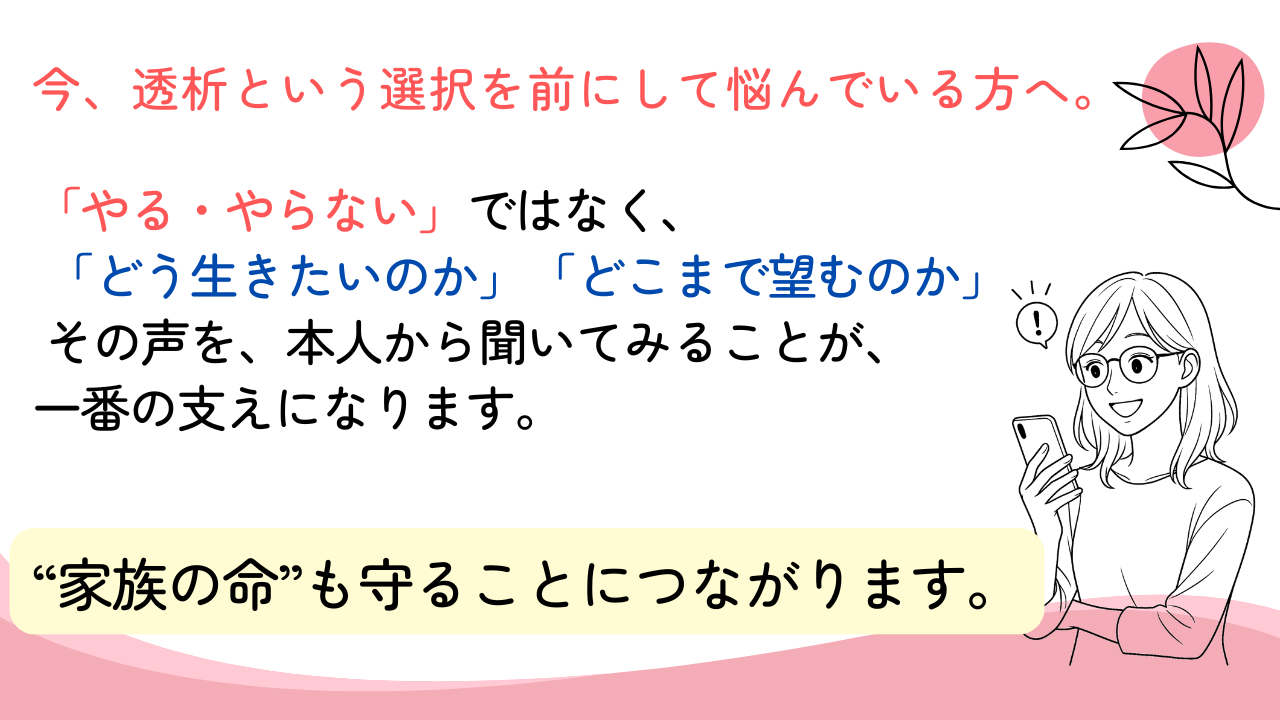
「やる・やらない」ではなく、
「どう生きたいのか」「どこまで望むのか」
その声を、本人から聞いてみることが、一番の支えになります。
家族だけで抱えず、
-
医師に「保存的治療(透析をしない)という選択肢はありますか?」と聞く
-
地域の在宅医療・包括支援センターに相談する
-
「本人と一緒に“生き方”を話し合う」機会を、今からつくる
それが、“家族の命”も守ることにつながります。
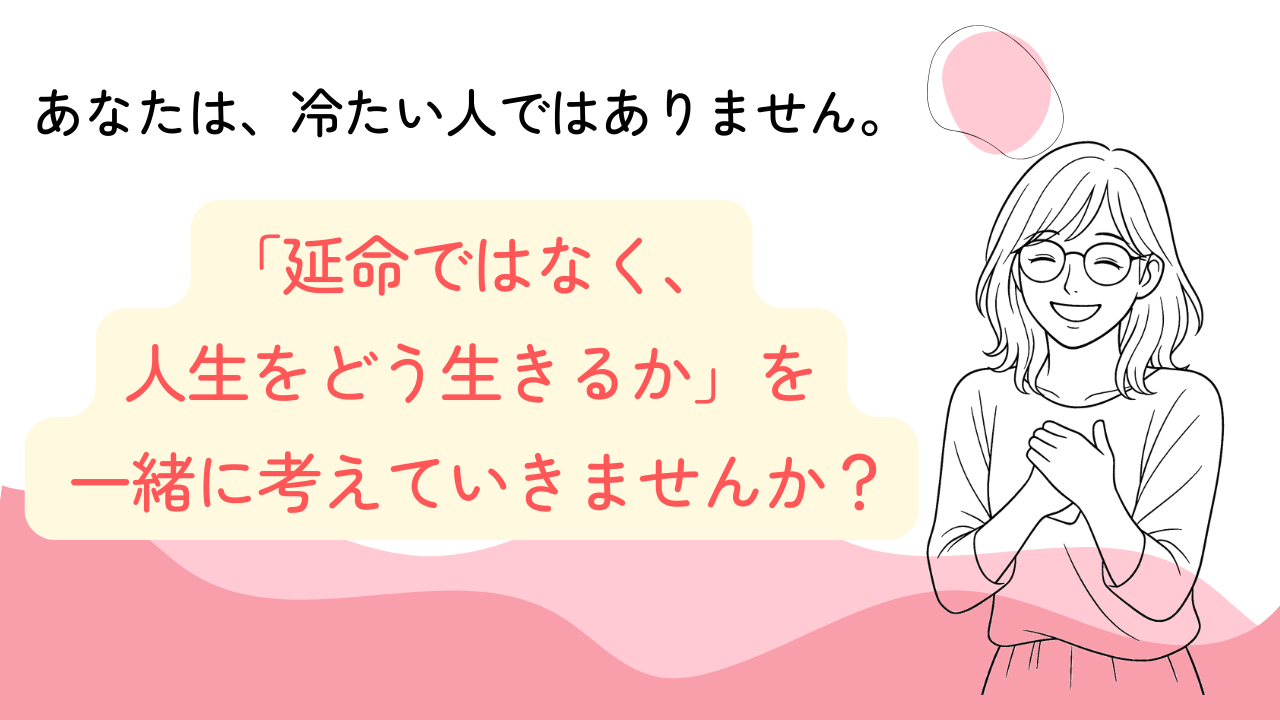
あなたは、冷たい人ではありません。
ただ、「誰も問い直してくれなかった選択」の中に、立っているだけ。
今ここから、
「延命ではなく、人生をどう生きるか」を
一緒に考えていきませんか?

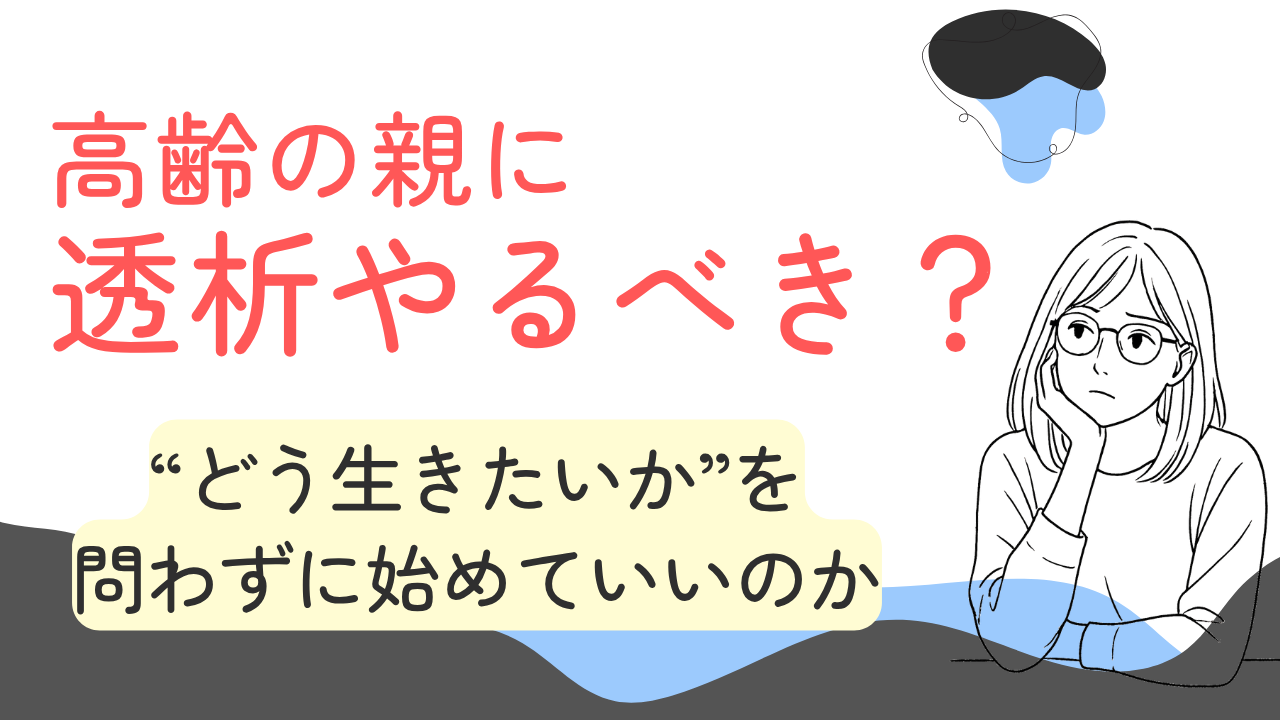
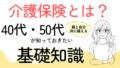
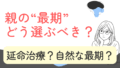
コメント