「延命は望まない」——そう思っている人は少なくありません。
けれども実際には、多くの方が“望まぬ延命”の末に、苦しみながら最期を迎えています。
その理由は、突然やってくるわけではありません。
実は、日常の中にひっそりと入り込んでいる“医療の前段階”が、その未来を静かに導いてしまっているのです。
延命の選択は、もっと前に始まっている
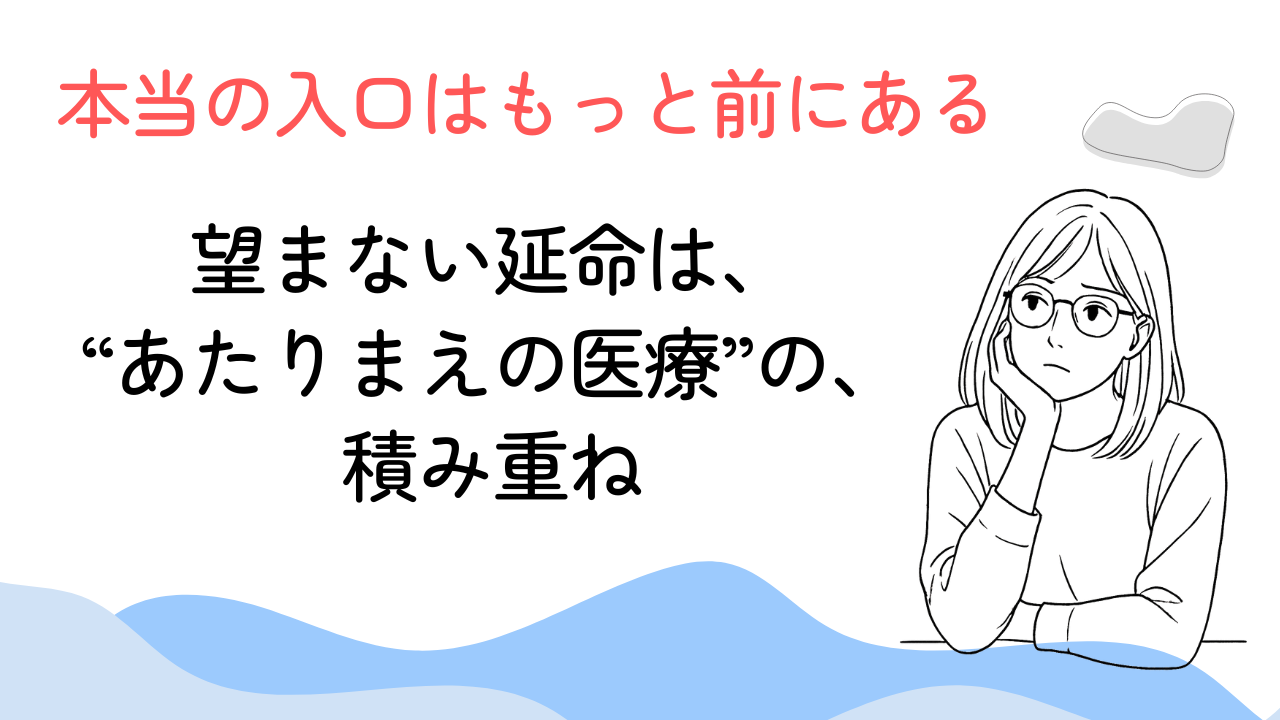
「延命治療をしますか?」と問われてから考えるのでは、実はもう遅いのかもしれません。
延命という選択は、突然降って湧いたものではありません。
長年続けてきた日々の医療行動——通院、薬、検査、救急への意識——
これらが知らず知らずのうちに“断れない延命”への道筋を作ってしまっているのです。
日常に潜む“前段階の医療”のパターン

以下のようなケースは、多くの方が経験しているのではないでしょうか:
- 毎月の通院、理由もわからず惰性で続けている
- 処方された薬を内容も効果も知らずに飲み続けている
- 「念のための検査」を当たり前のように受け続けている
- 不安なときに、迷わず救急車を呼んでしまう
これらは全て、生活の中に溶け込んだ“前段階の医療”。しかし、この積み重ねが延命の引き金になることを、私たちはあまりにも知りません。
望まない延命が始まる医療の構造

とくに高齢者に多いのが、救急搬送による延命のスタートです。
日本では、高齢者が救急車で搬送された際、
- 意識確認前に処置が開始される
- 医師が法的・倫理的責任から命を優先する
- 結果として人工呼吸器、心臓マッサージ、点滴などの延命措置が当然のように始まる
という構造が制度的に存在します。そこには「本人の意志」は、ほとんど反映されていないのです。
家族の後悔——ある女性の物語

80代のある女性は「延命はしない」と家族に伝えていました。
しかし、軽い発熱で病院に行ったことから、検査、入院、点滴…と処置が進み、気がつけばチューブだらけに。
娘さんは言います:
「気づけば、本人の“終わりたい時”を越えていました。私たち家族も、止め方がわからなかった」
これは特別な話ではなく、全国各地で起きている“静かな現実”なのです。
善意と制度が生む“断れない医療”
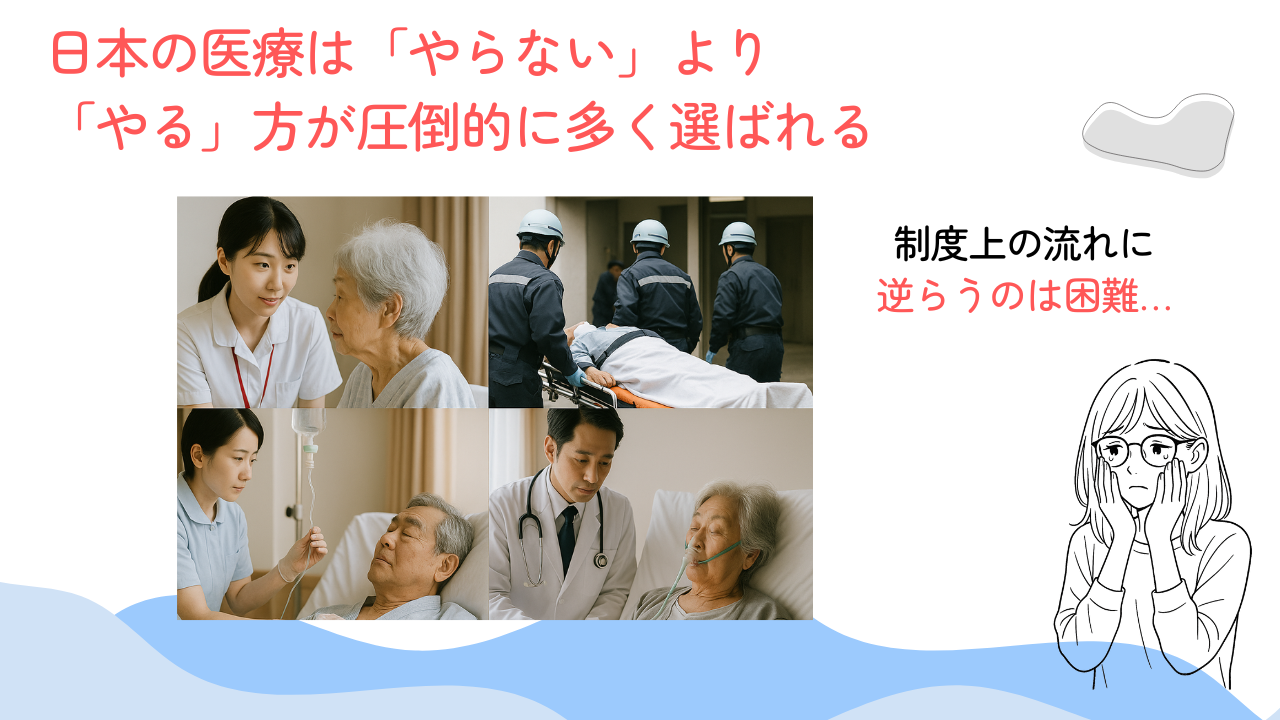
なぜ、こうした延命が頻発してしまうのか?
答えは、医療の制度設計と、関係者すべての“善意”にあります。
- 救急要請があれば、命をつなぐ処置が最優先
- 病院もリスク回避から延命措置を取る傾向
- 家族も混乱の中で「とりあえずお任せ」になりやすい
その結果、「やらない」より「やる」が常に優先される仕組みが完成してしまっているのです。
自分で立ち止まることが、唯一の予防策
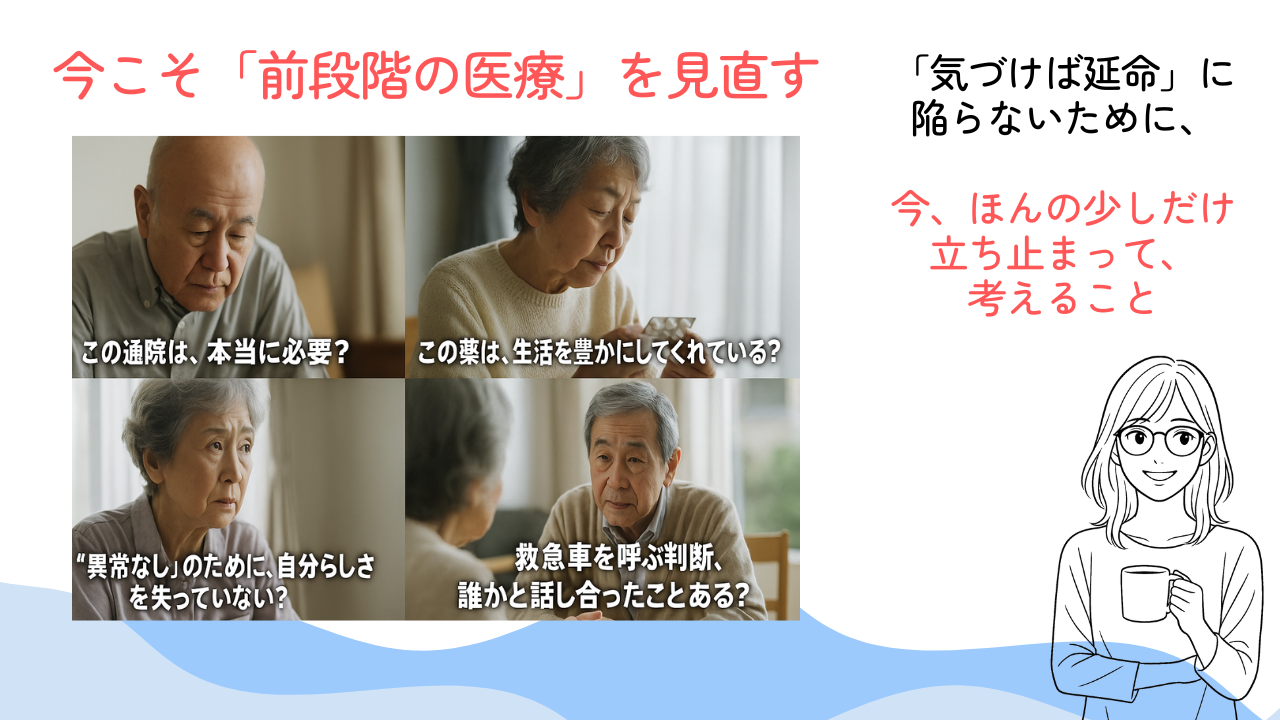
私たちにできることは、制度をすぐに変えることではありません。
まず、自分の医療との関わり方を見直すこと。
- 通院の意味を問い直す
- 薬を見直す
- 検査の目的を確認する
- 救急対応を家族と話し合う
これらはすべて、「延命を拒否する」ためではなく、「人生を自分で選び直す」ための行動です。
医療を“主役”にしない人生へ
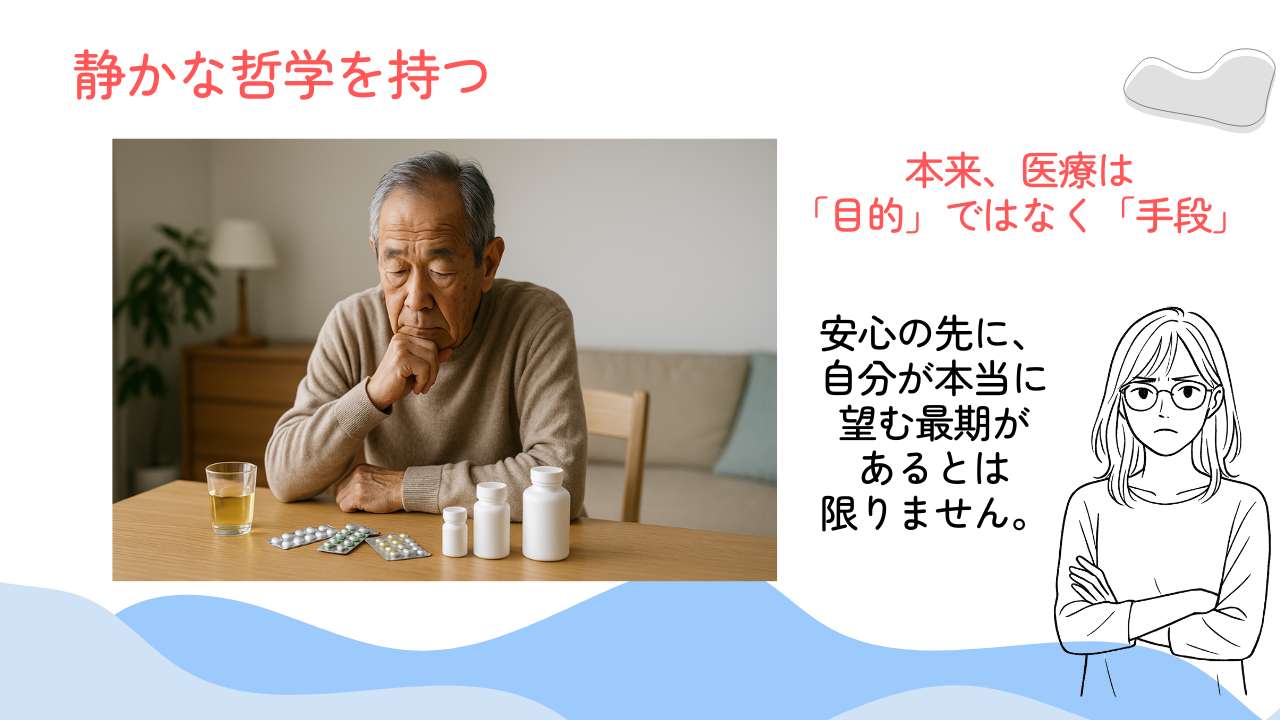
医療は手段です。けれど、今の社会では医療を「受け続けること」自体が目的化してしまっている場面が少なくありません。
- 数値を守ること
- 通院を続けること
- 薬を切らさないこと
これらが安心を与えてくれることもあります。ですが、その安心が自分の望む最期に結びついているかは、また別の話です。
哲学のまなざしから——“死”が照らす“生”

古代ギリシャの哲学者・エピクロスは、こう言いました。
「死は私たちの生き方を照らし出す」
延命を拒むことよりも、 「どんな最期を生ききるか」を自分で描くことの方が、ずっと難しく、そして尊い選択なのだと思います。
あなたへの問いかけ
このブログを読んだ後、どうか一度だけでも、問いかけてみてください。
- 今、私が続けている医療は、私のため?
- 「このまま最期を迎えても悔いはない」と言える?
その問いが、小さな一歩になることを願っています。

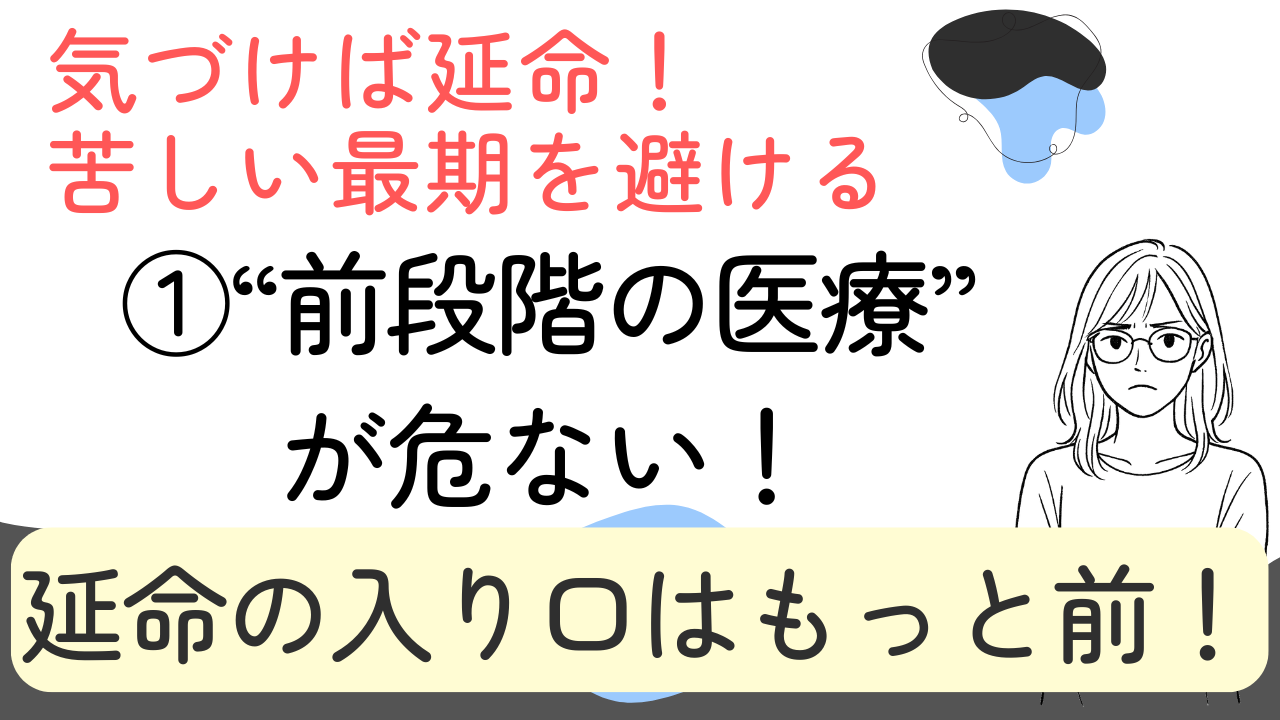
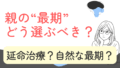
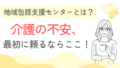
コメント